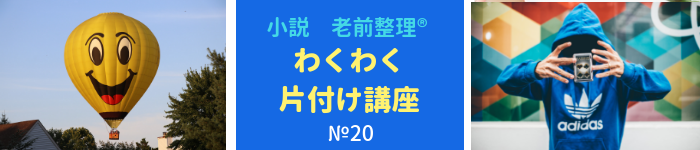老前整理 片付け 整理 終活 シニア 行動経済学 ひとり暮らし ロボット
20 、サポーター殺人事件(5)
いよいよ殺人事件が起こり、犯人はわくわく片付け講座の受講者?
武将の兜をデザインした柄のネクタイを勧めていた正美はくら子を見て、あっと声をもらし
た。
紳士は何事かと振り向いたが、正美はいえ、知り合いなものでとごまかして、下を向いた。
紳士はやはり兜は派手すぎるからいつものレジメンタルでと、ストライプのネクタイを手に
取った。
かしこまりましたと、正美はネクタイを手にレジへ向かう途中くら子にささやいた。
「30分したら休憩なので、3階のティールームで…」
ティルームは女性客でにぎわっていた。
「売り場はすいているのに、ここはいっぱいですね」
まろみは案内を待たずに奥に進み、くら子を手招きした。
メニューを手にしたまろみは、目を丸くした。
「コ、コ、コーヒーがおかわり自由で2000円。2人で4000円、ここはどこ?」
声が大きいと、苦笑しながらくら子はまろみをたしなめた。
だってとまろみは後の言葉が続かない。
「女は度胸。ここのティールームは高いので有名なのよ。それより正美さんもわかったみた
いね」
「あの、これは会社の仕事ですから必要経費にしてもらえるのでしょうか」
「その心配はいいの、それより正美さんのことに集中して」
くら子の言葉にまろみはほっとした。財布には千円札1枚しか入っていないのだ。
正美が現われたのは40分後だった。3杯目のコーヒーを前にして、くら子は正面から正美
の目をとらえた。
頬には汗か涙の跡があり、それを白粉で隠そうとしているが急いだせいかむらになってい
る。
正美は時間がないので、手短にお願いしますと浅く腰かけた。
「それでは単刀直入に申し上げます。どうしてお姉さんの和美さんになりすまして講座に参
加されたのですか」
ゴクンと喉が鳴ったが、正美は口を開かない。まろみもじっと正美を見つめている。
ウエイトレスが運んできた水を飲もうとする正美の手が震えている。
「姉になりすまして講座に参加したことが犯罪でしょうか」
いいえと、くら子は答えた。
「ただ、どうしてそんな事をしなければならなかったのか、お尋ねしたいと思いまして」
「そ、それは…ある人に頼まれて…」
「たぶん、そうだと思います。その方を信頼しておられますか」
正美は目をつぶってうなずいた。わかってはいても現実を認めたくないのだろうとくら子
は思った。
「わかりました。これ以上何を申し上げても無駄ですね」
くら子はきっぱりと言った。
正美は無言で立ち上がり、それではと言いかけてくら子に視線を戻した。
「どうして私が姉の和美になりすましているとわかったのですか」
「左手の甲に傷がなかったから」
ああ、和美の左手には…テーブルに両手をついて体を支えた正美はうなだれた。
正美さんと声をかけようとしたくら子を振り払い、正美は出て行った。
「これでよかったのですか?」
まろみの問いにくら子は肩をすくめた。
「正美さんも子供じゃないし、ご自分の考えで行動されるでしょう。今回の問題は正美さん
が和美さんになりすましたことでしょ。誰かがどこかでリサイクルショップを開くというの
は、また別の問題だから」
「しかし恵比寿さんや健さんの商売が…」
「商売敵が現われるのは当たり前。そんな事でつぶれるくらいならとっくにつぶれているわ
よ」
「今日はいやに強気ですね」
「コーヒーを5杯も飲んだから…」
「2000円を割る5だから一杯400円、それなら元はとっているかも」
事務所に戻ったくら子は古書店「ぽんぽん堂」の恵比寿に電話をした。
事情を聞いた恵比寿は「ひきとりや」の健さんにも連絡しておく、また何かあったら知らせ
てくれるようにと結んだ。
「正美さんはもう講座には出てこないでしょうね」
くら子はたぶんと答えたものの何事も起こらなければいいがと思った。
3日後、まろみが30分遅刻をして事務所に飛び込んできた。
「また、二日酔い?」
「ち、違いますよ。テレビのニュースで、ま、ま、ま」
はいはい落ち着いてと、くら子はまろみに水を持ってきた。
肩で息をしながらまろみは一気に水を飲み干した。
それでと、くら子は向かいの椅子に座った。
「ま、正美さんが、あのバツ4の男とドライブに行って、崖から落ちたらしいです」
くら子の顔色が変わった。
「詳しいことはわからないのですが、正美さんは助からなかったようで」
「というと…」
「男は重傷だけど命は助かったようです」
苦い沈黙が漂った。
くら子とまろみは近所の喫茶店に行き、マスターに頼んでテレビのチャンネルをワイドシ
ョーに替えてもらった。画面は崖の上から谷底のつぶれた車を映している。
キャスターはスピードの出しすぎの事故か、心中かわからないと言っている。
おしぼりを握りしめてくら子は画面のキャスターに向かい、心中の訳ないでしょとつぶやい
た。まろみも珍しくじっと画面を見つめている。
くわしいことはわからないまま番組は別の話題に移った。
事務所に戻ると、廊下で恵比寿が待っていた。
「えらいことになったな」
立ち話もできないからと、くら子は鍵を開けて恵比寿を中に入れた。
「あの、わたしたちが原因でしょうか」
おずおずとまろみが、聞いた。
「いや、そんなはずはないよ。不動産屋の話によると岸田は店の手付金を打ったらしいか
ら、改装してオープンするつもりだったんじゃないかな」
「単なる事故には思えないのですけれど」
くら子の言葉に恵比寿はうなずいた。
「正美さんも騙された口かもな」
恵比寿のため息にくら子も黙り込んだ。
あれ、ノックの音がしませんでした? とまろみがドアを見た。恵比寿とくら子が首をかし
げると、まろみは勢いよく立ち上がった。
ドアを開けたまろみは、あわわ、ゆ、幽霊と、ドアを指差したまま、壁に寄りかかり、そ
のままずるずると座り込んだ。
くら子が慌ててかけよった。
恵比寿が半開きのドアを開けると、廊下に青い顔をした女がぼんやり立っていた。青白くむ
くんだ顔は素顔で、ブラウスのボタンを段違いにかけ、ジーンズの足元は素足にスリッパだ
った。とにかく中に入ってくださいと恵比寿が女の手を引き、抱えるようにしてソファーに
座らせた。
まろみは腰が抜けたらしく、立ち上がれずあわあわ言っている。
「おい、まろみちゃんは大丈夫かい?」
恵比寿は振り返って尋ねたが、くら子はしばらくじっとしてなさいねとまろみの腕を軽く叩
いた。
「大丈夫、びっくりしただけですよ。それよりこちらの方が先決です」
くら子は、冷たい水の入ったグラスを女の前に置いた。
女はブラウスにこぼれるのも気にせず水を飲みほした。
グラスを握ったままうつむいている女に恵比寿は聞いた。
「あなたは…正美さん?」
女はうなだれたまま力なくうなずいた。
「事故のことはご存知ですね?」
恵比寿の問いに、正美はわっと声をあげてテーブルに突っ伏せた。
この場面を見逃すものかと、まろみが四つん這いで床をはってソファーまでたどりつき、く
ら子と恵比寿がよっこらしょと抱えあげて座らせた。
腰を下ろしたとたんにまろみは正美に足があるのか、テーブルの下を確かめている。
くら子は小声でまろみに、幽霊じゃあないわよとささやいた。
2杯目の水を飲み終えた正美はようやく落ち着いた。
「なにからお話ししていいのか…」正美の声は震えている。
恵比寿が事故のことはいつ知りました? と聞いた。
「今朝のテレビで…」
「ニュースでは貴女が車に乗っていたことになっていましたが…」
正美は唇を震わせて、違うのですと答えるのがやっとだった。
「それでは、車に乗っていた女性は?」
「そ、それが、あの『サポーター講座』に参加していた人なんです」
くら子とまろみはぎょっとして顔を見合わせた。
「だ、誰なんですかー」
腰をさすりながらまろみが上ずった声をあげた。
「それが、お名前は忘れましたが、おばあさんにきものをもらってNPOをクビになった人で
す」
くら子は竜崎貴美香のことだと思ったが口には出さなかった。
「それでは、どうして正美さんが事故にあった事になっているのですか」
くら子の問いに正美はぽつぽつと語りだした。
正美は岸田とドライブに出かけた。高速のサービスエリアでトイレに行き、車に戻ると助
手席に女が座っていた。それも「サポーター講座」に参加していた女だった。
正美はこれはどういうことかと岸田をなじった。
岸田は後ろに乗れと言い、正美が仕方なく乗ると車は走り出した。助手席の女は後ろを向い
て、これは「わくわく片付け講座」なのよと答えた。
「どういう意味ですか」
正美が聞くと、女は鼻で笑った。
「だから邪魔な女を片付けるのよ、わくわくするわ」
「そんなばかなこと、岸田さんこれはどういうことですか」
岸田は黙ったままで、女の高笑いだけが車内に響いた。
「知らぬが仏とはこのことね。おバカさん! 岸田さんは保険金目当てに決まっているでし
ょう。そうでなければ8つも年上のおばさんと結婚するなんて言わないわよ」
おい余計なことを言うなと、岸田が女をにらみつけた。
「ほ、保険ってどういうことですか、岸田さん」
正美はすがるような思いで岸田に問いかけた。
女はまだわからないのとせせら笑った。
「わたしたち結婚するって…だから」
「あたしがいるのに、するわけないでしょ。あんたの保険金であたしたちが商売するのよ」
正美は頭の中で騙されたことを認めたくない自分と、この2人に「片付けられる」自分を考え
ていた。車のロックは外せそうにない。
「気分が悪い、吐きそう」
「フフフ、もうすぐそんな心配しなくてもよくなるわよ」
正美は体を折り曲げて、喉に指を突っ込み、声を上げた。
「おいおいこれは新車なんだぜ、それを汚されては…」
岸田が路肩に寄せて車を止めた。
車を出た途端に正美は、助けてぇー、誘拐、拉致ですぅーと大声で叫びながら走り出した。
岸田は追いかけようとしたが間に合わず、慌てて車に飛び乗り、走り去った。
正美がとぼとぼと歩いているところにトラックが止まり、乗せてくれた。
バッグは車の中で無一文だった。
体を引きずるようにしてマンションに帰った正美は、玄関に足を踏み入れた途端に崩れ、
そのまま眠ってしまった。
朝、玄関で寒さに目を覚まして、夢を見ているのかと思ったが泥だらけの体と汚れた服をみ
ると、現実だということがわかった。
シャワーを浴びながら昨日のことを思い返した。
バスローブ姿でオレンジジュースを片手にテレビをつけると、事故のことが報道されてい
た。
なぜ、昨日あのまま警察に行かなかったのか。ぼんやり考えていると、二ュースキャスタ
ーの口から自分の名前が読み上げられ飛び上がった。
車はガードレールを突き破り、崖から転落、炎上して黒い塊になっていた。
正美はテレビの前で茫然とした。携帯電話も車と共に燃えただろう。姉の和美にこんなこ
とを話せない。警察に行くのもためらわれた。そこでくら子とまろみのことを思い出した。
えらいことになったなあと、恵比寿は正美から目をそらした。
「とにかく、警察へ行って事情を話した方が良いのではないですか」
くら子の提案に正美はかぶりを振った。
「いずれにしろ、事故に遭ったのが正美さんでないことを知らせなくては」と、くら子は恵
比寿に目くばせをした。やれやれという顔で恵比寿が立ち上がった。
2人が出て行くと、まろみがしゃべりだした。
「わたしも一度警察の事情聴取とやらに立ち会いたかったのに」
「なに、言ってるのよ。幽霊だと思って腰を抜かしたくせに。しかし本当に腰が抜けるってあ
るのね、初めて見たわ」
「冗談じゃありませんよ。それより正美さんはどうなるのでしょう」
「さあ、彼女の話だけでは詳しいことはわからない。とにかく生きていることは確かだか
ら」
仕事を終えて事務所のドアに鍵を掛けようとしたくら子に、まろみがまた幽霊ですとささ
やいた。
恵比寿が昼間とは別人のような顔で立っていた。
「お疲れさまでした」とくら子が声をかけても、恵比寿は硬い表情を崩さなかった。
「話がある」
事務所に戻ろうかとドアを開けようとしたくら子を制し、恵比寿は飲まないとやってられな
いと言った。
居酒屋の小上がりの座敷の隅で、恵比寿は黙ってジョッキのビールを口に運んだ。
くら子とまろみも、いつもと様子の違う恵比寿に緊張していた。
恵比寿は1杯目を飲み干すと、ひとごこちがついたように、ふーっと息を継いだ。
「あれ、2人は飲まないの?」いつもの恵比寿に戻っていた。
「恵比寿さんが何も言ってくれないから、飲めないんです」
まろみが口をとがらせた。
「悪い悪い、いや、どうぞ、1杯やってください。話はそれから」
恵比寿は2杯目を頼んだ。
「実はね、えらいことになってる」
ようやくビールを口にしたまろみの目の周りが赤くなり、目がきらきらと輝いている。
「正美さんは殺されそうになって逃げたんでしょ」
「そうなんだが…」
「危機一髪でしたね。ドラマのヒロインみたい。しかし保険金殺人だなんて、新聞やテレビ
のドラマの中だけだと思っていたけど、自分の知っている人が殺されそうになるなんて」
まろみはこれで事件が解決したと思っているようだが、なんだかしっくりこないくら子はジ
ョッキを置いて恵比寿をじっと見た。
「実は…車のブレーキに細工がしてあったそうだ」
まさかと、くら子は手で口を押さえた。
「そのまさかなんだよ」
「えっ、どういうことなのですか。なんですか? わたしにも教えてくださいよ」
まろみは恵比寿とくら子にきょろきょろと目を走らせた。
「警察はブレーキに細工をしたのは正美さんだと疑ってる」
まろみがブワァーと、ビールを吹き出した。
おいおい、これだから困るんだよなあと言いながら、恵比寿はおしぼりで背広の袖を拭き、
くら子もほんとうにねと相槌を打ちながら、から揚げの皿を移動させた。
事件の真相が次々に明るみに出ると、くら子とまろみは茫然とした。
重傷を負いながらも話ができるまでに回復した岸田が証言をしたからだった。
デパートのネクタイ売り場で正美を引っかけたつもりの岸田が、実は引っかけられていた
のである。お互いに本性を隠して結婚話はとんとん拍子に進んだ。
事業に失敗していた岸田は正美に結婚とリサイクルショップの話を持ちかけた。そして友人
が保険会社に勤めているが、契約が取れなくて困っているから2人分の契約が取れれば助かる
と、お互いを受取人にして契約を結んだ。
岸田はリサイクルショップの件に関しては自らが表に出ず、正美がすべて進めていること
にした。正美が調べると、リサイクルショップ「ひきとりや」のほかに古書店「ぽんぽん
堂」そしてそのグループに「わくわく片付け講座」が含まれていることを知った。
偶然か幸いと言うべきか、姉の和美が以前その講座に参加したことを知った正美はそれを
利用して和美になりすまし「サポーター講座」に参加し、ついでにその講座もつぶそうとし
た。
次にどうやってつぶすかだが、手始めに講座に参加していた竜崎貴美香を利用することにし
た。
傾聴ボランティアの訪問先で着物を受け取った貴美香に、高値で着物を買い取ってくれる
処を紹介する、また仕事がなければ、そこで働かないかと持ちかけたのだった。
ここまではうまくいったが、くら子とまろみに偽者だと気づかれた正美は焦って計画を変
更した。元々岸田に愛情があったわけでなく金目当てに近づいたので、リサイクルショップ
もどうでもよかった。そこで一石二鳥とドライブと称して岸田と貴美香を誘い出し、車のブ
レーキに細工をして2人が事故にあったと見せかけ、自分が被害者になりすました。
2か月後、恵比寿とくら子、まろみの3人は居酒屋にいた。
あれから恵比寿もくら子たちもテレビのレポーターや雑誌の記者に追いかけられた。正美が
貴美香と知り合ったのが「サポーター講座」だったからで、警察に行くのに付き添ったのが
恵比寿だったからである。
お陰で「わくわく片付け講座」は開けず、今の言葉でいえば「炎上」状態で、事務所の電話
は鳴りっぱなし、口に出せないような不愉快なことが山ほどあった。
まろみがしみじみ言った。
「しかし、正美さんが一番の黒幕だったとは思いもしませんでした」
まろみの正直な感想に恵比寿とくら子もうなずいた。
「ほんとにな、K社に来た時にはまさしく被害者のようだった。3人ともすっかりだまされた
わけだ」焼き鳥の串を片手に恵比寿はしみじみ言った。
まろみはうり二つの和美のことを思い出した。
「先日、お姉さんの和美さんが事務所に来られたんです」
恵比寿は空いている手でジョッキを手にして、あの人も大変だっただろう。それでと聞い
た。
「ご迷惑をかけて申し訳ありませんでしたって」
ううむと恵比寿はうなり、ご迷惑なんてものじゃなかったなとつぶやいた。
「わたしが和美さんに電話をかけた時に、正美さんのことを話していればこんなことにはな
らなかったのかもしれませんと言ったんです」
彼女はなんと? と恵比寿は先を促した。
「どちらにしろ、結果は同じだったでしょうって」
妹の正美は子どものころから息をするように嘘をついた。それもただの嘘ではなく、気に
入らない相手を陥れる悪意の嘘だった。普通なら嘘をついていることにどこかでやましさを
感じるものだが罪悪感はまったくなかった。同じDNAを持ち、同じ環境で育った双子なのに
どうしてこうも違うのかと和美は不思議でならなかったそうだ。
「姉妹でもわからないのだから、我々がわかるはずもないな」
自嘲気味の恵比寿の言葉に、2人は頷いた。
「それで、いつから講座を再開するの?」
「来月からのつもりですけど、人が集まるかどうか…」
くら子の重い口調にまろみが付け加えた。
「世間では『わくわく片付け講座』を、邪魔になった夫を始末する講座だと噂してます」
「ほう、それじゃあ参加者は増えるだろうな」
苦笑と共に、くら子は1つ残っていた疑問を口にした。
「どうして陸奥慶子さんは講座の受講者にスパイがいるってわかったのかしら」
まろみが当然のように答えた。
「そりゃあ、動物探偵だから鼻がきくんですよ」

これでサポーター殺人事件は終了です。
短い話だけアップするつもりでしたが、どうせなら長いのも載せようと、予定を変更して、5
回に分けてアップしました。
最後まで読んで下さった方に感謝

「くらしかる」(HP2) ご案内 

 |
 |
||||
 |
 |
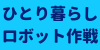 |
「くらしかる」(HP1) ご案内 
 HP1ヘ
HP1ヘ  |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
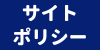 |
 |
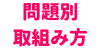 |
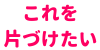 |
◆「老前整理」は(株)くらしかるの登録商標です。無断での商用利用はお断りします。