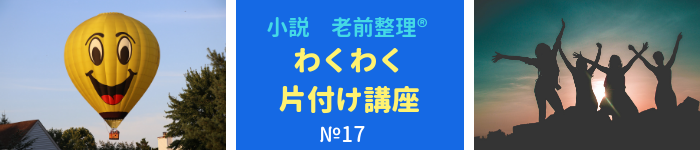�V�O�����@�Еt���@�����@�I���@�V�j�A�@�s���o�ϊw�@�ЂƂ��炵�@���{�b�g
��17 ���ʂ܂Ō��C�N���u�@
�@�@�@�u����ꐶ�v���ݗ��̎�|�@
�@�@�@
�悤�ɑ�ʂɎ���|���o���Ă���B
�@���A�������̃h�A���J���āA������̃X�C�b�`������������q�́A�ڂ̑O�̌��i�ɗ�����
���B���ɔ��������L�����Ă���B��u�A�D�_���Ǝv���ジ���肵�������Ɉُ�͂Ȃ���
�ŁA���鋰��ߊ���Č���ƃt�@�b�N�X�̎��������B
�@���Ⴊ�ݍ���Ŏ��������Ă���ƁA�܂�݂��������Ȋ�ł��͂悤�������܂��ƌ��ꂽ�B
�u����q����A�Ȃɂ��Ă��ł����v
�u��ʂ̃t�@�b�N�X�������݂����ŁA���̒ʂ��v����q�͊�������߂��B
�u���������āA��������Ƃ��A���₪�点�H�@�����ł��˂��v
���ꂪ�����ł��Ȃ��݂����ƁA����q�͎茳�̎��ɖڂ�������B
�@�t�@�b�N�X�͎����Ȃ��Ȃ�����́A���F�������v���`�J�`�J���Ă���B
�u�ǂ��������Ƃł����v�܂�݂������W�߂��B
�u���ꂪ�A�w�r�f�b�x���āA�m���Ă�H�v
�u�����A���������ƂȂ��ł��ˁB��������A�����ۂ�A��������W�܂�Ƃ��c�V�j�A�S�[��
�h�N���u�A���ꂾ�ƃJ�[�h��Ђɂ��肻�������ǁB�V���O���K�[���N���u�A�Z�N�V�[�M����
�N���u�ȁ[��āA������Ƃ������킵�����ǁA���肻���ȁc�C�q�q�v
�u���̂ˁA�Z�N�V�[�M�����������Ȃ��ł���B�S���A����́w�킭�킭�Еt���u���x�̐\
�����݂Ȃ̂�v
�u�ق�Ƃ��A����ԍ��܂ŏ����Ă���v
�u�ł��A�ǂ��̉�����͂킩��Ȃ��B�����ƌ���������50�l�͒����Ă�ł��傤�v
�܂�݂͗����オ��A�e�`�w�̑���Ղ̊W���������B
�u�����Ȃ��Ȃ��Ă܂��B������ꂽ��܂��܂����邩������܂���B�ǂ����܂��H�v
�u�Ƃɂ����A�������Ă݂āv
�@�t�@�b�N�X�Ɏ����Z�b�g���Ȃ���A�܂�݂͂܂��l���Ă���B
�u���ɁA�Ӗ��ɁA����߂Ⴑ�ŁA�r�f�b�v
�u�͂��H�@���x�͉��Ȃ́v
�u�ӂ肩�����D��Ȃ�A�����Ȃ�܂��v
�Ȃ�قǂƌ����Ȃ���A����q�͘A�Ȃ����\�������ꖇ�ꖇ�͂��݂Ő藣���Ă������B
�܂�݂��t�@�b�N�X�̊W��߂��r�[�ɁA�s�[�Ɩ�A�܂��Y�Y�Y�Ǝ����͂��������B
�u���ꂥ�[�A�ǂꂾ�������ł���v
�u�V�L�^���ǂꂾ���X�V���邩�����̂˂��v
����q�̓t�@�b�N�X�����āA�ʔ������ɘr��g�B
�u�������A����q����A����ł́c�v
�u�ʂɁA�V�n���Ђ�����Ԃ�����ł͂Ȃ��̂�����S�z���邱�ƂȂ����B������t�@�b
�N�X�̎��͂܂�������������v
�u�����u���͂���ŏI���ł��v
�u���w�Z�̑O�̃u���u�����Ŕ����ė��Ă����H�v
�@�܂�݂��������ɖ߂������A����q�͓d�b���������B�t�@�b�N�X�͂܂��������Ɠ����Ă�
��B
�u���̃t�@�b�N�X���V�����̂Ɋ�����A���������炯�ɂȂ邱�ƂȂ��̂ɁA���������Ƃ�
�낪�P�`�Ȃ���c�v
�d�b���I���������q�́A�܂�݂������Ƃɂ�B
�u�����ƁA�������Ă���B�Â�����Ƃ����Ă܂��g������̂��̂Ă�킯�ɂ͂����Ȃ�
�ł��傤�v
�͂��͂��A�Ɠ�����܂�݂Ɂu�n�C�͈��ł����́v�Ƃ�������q�̐�����ԁB
�܂�݂����q�ɂ̂��ĕ������B
�u�Ƃ���ŁA���̒��팻�ۂ͂ǂ����痈���̂ł����H�v
�u����́A���팻�ۂł��A�S�쌻�ۂł��A�V���N���j�V�e�B�ł��A������d���̎d�Ƃł���
��܂���v����q�͒f�������B
�@�F���l��s�v�c�Ȃ��Ƃ���D���Ȃ܂�݂͌��𗎂Ƃ����B
����q�͒�����̑����ł�����������A�R�[�q�[�ł�����܂��傤�Ƒ䏊�Ɉړ������B
�u����������A�����l�����������݂����ŊÂ����̂��~�����Ȃ�܂����v
�ƁA�܂�݂̓N�b�L�[�̊ʂ�����Ă���B�Ȃ��悭�킩��Ȃ�����������NjC�����͂�
����ƁA����q�̓}�O�J�b�v�ɃR�[�q�[�𒍂����B�܂�݂̓`���R�`�b�v�N�b�L�[��������
�Ȃ��畷�����B
�u����ŁA���̃i�C�A�K���̑�̂悤�ȃt�@�b�N�X�͂Ȃ�Ȃ̂ł����v
�@�i�C�A�K���Ƃ̓I�[�o�[�˂��ƁA����q�͏��ăR�[�q�[���������ł�����������B
�@����q�̌Â��F�l�̃}�L�E�f�E���u�����N�O����Ǝ��]�_�ƂƂ��Ċ��Ă���B�����N
�̏����Ɍ����Ă̍u�����������Ă��������ɁA�t�@���N���u���ł��A���ꂪ���W����SGC��
�����c�̂ɂȂ����B�����́A�C���h�̃A�V�������փ��K�̏C�s�ɍs������A�t�B�����c�F�}
���\���ɎQ��������A�g���R�����𖡂키����������ł���B
�u���́A�}�L�Ȃ�Ƃ�������āA�O�l�ł����v
�u��㐶�܂�̑��炿�̓��{�l��B�C�M���X�̐l�ƌ������āA10�N���炢�������ɂ�����
�����v
�u�Ǝ��]�_�Ƃ��Ă悭�킩��Ȃ��̂ł����v
�u����Ɍ�����������Ȃ��́B�悭�m��Ȃ����ǁv
�u�Ȃ��₽���������B�͂́`��A���̐l�������Ȃv
�u�����Ȑl�Ƃ͗F�B�ɂȂ�Ȃ����B�����Ȑl�͒P�Ȃ�m�荇���ƌ����܂��v
�u����ŁA����ŁA�r�f�b�́H�v�܂�݂͐g�����o�����B
����q�͏������ݎE���Ȃ��瓚�����B�u���ʂ܂Ō��C�N���u�����āv
�u�c�N���u�����ł����A�ςȂ́v
�u�v����ɁA"�s���s���R����"�v
�͂��H�@�s���R�������ł����ƌ����Ȃ���A�܂�݂͂�������O�ڂ̃N�b�L�[����ɂ���
�����B
�u�܂�݂����͒m��Ȃ������H�@���ʑO�܂Ńs���s�����ĂāA�R���b�Ɛ���������]�v
�u�����̂���������Q�肵�Ă��鐼����"�ۂ����肳��"�݂����Ȃ��̂ł����˂��v
�u����͂��n������ł���B���̐l�����́A���͂Ŋ撣���Ă�݂�����v
�@�܂�݂�4�ڂ̃N�b�L�[�Ɏ��L���āA����q�ɉ�������ꂽ�B
�u�������߂��v
��܂����[�Ɠ��������Ȃ���A�܂�݂̓t�@�b�N�X�ɖڂ��������B
�u�A�b�A�~�܂��Ă�v
�ق�Ƃ��ƁA����q�͂܂��g��ł��Ă��鎆�������W�߂��B
�܂�݂͂�����ƈ֎q����]�����A�ǂ����Ă��̐l�������\�����̂ł����Ƌ^�������
�����B
�u�}�L���A�r�f�b�̐V�N��ŏЉ���炵���́v
�@�\�������m�F���Ȃ���A����q�́A����̕��ϔN��͌\��㔼�ƌ����������B
�u�ł��A�Ǝ��]�_�Ƃ̃t�@���N���u���Ȃ��r�f�b�Ȃ�ł����v
�u�}�L����͎蔲���Ǝ��̒҂Ȃ́A����Ŏ��Ԃ�����Ă����Ȃ��̂�������H�ׂ�
��A�S�̉h�{�ɂȂ�悤�ȑ̌������܂��傤�B�y���Ď��ʂ܂Ō��C�ł���낤�A���Ă���
�̂��R���Z�v�g�炵���̂�v
�u�Ȃ�ƂȂ��A�t�@���ɂȂ�̂��킩��悤�ȁc�v
�u�}�L����̘b�ɂ��ƁA�s�v�ȕ����������邩��A�Ƃ������Ȃ��āA�|������Ԃ���
���邵�Ǝ���������B�����ł����́w�킭�킭�Еt���u���x���Љ�Ă��ꂽ�킯�v
�u�������A�}�L����̉e���͂͂������ł��ˁv
�u�����˂��A�ŋ߂̓J���X�}�炵������B����ɁA����̐l���������S�A�ו������炵��
���A�g�y�ɂȂ肽���Ǝv���Ă炵���̂��Ⴀ�Ȃ�������B�����փ}�L���ۂ�ƂЂƉ���
�������̂�����A�h�b�J�[���v
�u���x�̉��ɂ͓��肫��܂����v
�u�}�L����ɘA�������āA���������߂ĘA�����邱�Ƃɂ�����B���O�ɘb�����Ă����Η�
�������̂�����ǁA���̐l�͒i���Ƃ��A���Ƃ��Ƃ͖����̐l������v
�u�Ђ��[�B����Ȑl���A�Ǝ��]�_�ƂȂ̂ł����v
�u�����}�l�[�W�����g�����Ă��邩��A�{�l�͌�����������Ȃ̂�B���������K�i�O��
�̐l������A���{�ł͂��܂��������Ȃ�����ƃC�M���X�ɍs�����̂�B���オ�ς���āA
����Ȕޏ��ɖ��͂�������l���吨����炵���v
�u����ł́A����̍u���͂����ʂ�ł��ˁv
�u�����A�����ɂł��}�L����̂Ƃ���ɍs���āA�r�f�b�̌��͑��k���Ă��邩��v
�@�����̌ߌ�A����q�̓}�L�̃}���V������K�ꂽ�B�C���^�[�z���Ŗ����ƁA�ǂ�����1�K
���փz�[���̑傫�ȃh�A���J�����B18�K�ŃG���x�[�^�[���~���ƁA�S�[���h�̃W�����v�X
�[�c�𒅂����炫��̃}�L�������Ă����B�F���l���Ǝv�����ł����B
�u�}�L����A���̈ߑ��́H�v
�u����H�@�����A�F�ŃG���r�X�ɉ�Ƀ����t�B�X�̃O���C�X�����h�֍s������A���̎���
���߂̈ߑ��̉��D�����v
�@�W�����v�X�[�c�̑���U��ƁA�����t�����W���h��A�܂䂳���������B�S�[�W���X�ŏ�
�藧�Ă����r���O��z�����Ă�������q�́A�ڂ����������B
�@�a���ŏ��̊Ԃ�����A���ɂ͏�q���͂܂�A�Ƌ�ƌ�������ƒ��I�����������B
�t�����W��|���Ȃ���}�L�͍��z�c�����߂��B
�u�т����肵���H�v�}�L�͊y���������B
�u�����A�\�z�O�ł����v
�u�C�M���X�̐����ł킩�����̂́A�̂̓��{�̏�̐����������ɑf���炵�����Ƃ������ƁB
���̕������ƁA���|�����A�������Ƃ͂����������āAⴂłςς��Ƒ|�����������v
�@���̎���ɁA�͂�����ⴂ̂���Ƃ��ǂꂾ������̂��B����q�ɂ͐V������̂ɂ�������
������������ꂽ�B
�u�m���ɁA�C�����ǂ������ł��ˁc�v
�u����q�̌����������Ƃ͂킩����B�N���������֎q��x�b�h�̐������y�����Ă���
�́A�ł��ˁA10�N��20�N��ɔ�������A�����ɂ������̂�B�G���ɂ��Ȃ��Ęa������
�������Ă��āA�ǂꂾ����ɐQ�]�����Ď葫��L�������Ǝv�������Ƃ��v
�m���ɁA���̂��C�����͂悭�킩��܂��Ƃ���q�͓������B
����q����A����ɂ��͂Ƃ��~����ɁA�}�L�̖��̃P�C�����ꂽ�B
�u�܂��A�o����̂�����Ȃ�������������Ă��ł���B���ꂱ�ꌾ���Ă邯�ǁA���
�������������Ȃ���������B���̂����O���邩��v
�@�}�L�̓t���Ɖ����������B���������Ƃ���͐̂ƕς��Ȃ��B�P�C�Ƃ���q�͊��������
���ď����B�Ԓ��̉��ɂ͑�Ă����Y�����Ă����B
�}�L�͂ނ���ނ���Ɠ������Ă��ɂ��Ԃ�����B
�u����ŁA�r�f�b�̐l�������ǂǂ��ƃt�@�b�N�X�𑗂������āv
����q�͐K�������Ă���������Ȃ���A�����ł��Ɠ������B
�P�C����Ă��̓���������Ȃ���A�o����܂�����������̂ƃ}�L���ɂ�B
�u����ŁA���������������̂͂r�f�b�́w�킭�킭�Еt���u���x�̌��ł����ǁv
�u�����A����͂���q�̓s���̂������Ɍ��߂āA�P�C�ɘA�����Ă��ꂽ�炢������v
�u�͂��A�킽���̕��ʼn�ꂻ�̑��̃Z�b�e�B���O�����܂�����A�������}�L���Ǝ��]�_
�ƂƂ͋����܂����v
�u�����ł���B���̂킽���������̂��Ȃ��ǁA����ȂɉƎ������Ȃ��l���������̂Ɂv
�u������A������Ȃ��B�����Ɏ�����A���ꂾ�����l���Ă�������B���܂���
�F�l�̕ҏW�҂ɂ��̂��Ƃ�b������A�����Ȃ����́v
�u���̒��킩��Ȃ����̂ł��˂��v
�u�ق�Ƃق�ƁA������l���͖ʔ����̂�v
�@�������Ԓ������݂Ȃ���A����q�͏��̊Ԃ̊|�����ɖڂ�������B
���X�Ƃ����傫�Ȑ����̂��鎚�Łu����ꐶ�v�Ə�����Ă����B����q�̎����ɋC�Â��ă}
�L�͐u�����B
�u������A�킽���炵���Ȃ��H�v
�u�����A���������Ӗ��ł͂���܂��A�w����ꐶ�x��"���ʂ܂Ō��C"�ƂȂ����Ă���
�̂��ȂƎv�������̂Łv
�u�A�^����B�킽�������낢��l�����킯�v
�@�}�L�́u����ꐶ�v�́A����ňꐶ���I����Ă������̂Ȃ������߂��������Ƃ����v����
�炾�����B���������͊w������̉��t�̎��B��w����F�l���ł����A���т������ė�������
��Ă����}�L�𗝉����A�����ɂ��Ȃ����Ɨ�܂��Ă��ꂽ�l�������B
70���߂��A��w�̖��_�����ƂȂ������t�͊y�������Ƀ}�L�ɘb�����B
�u�킽���̓��̒��ɂ́A�_���̃A�C�f�A������10���炢����̂ŁA�̂�т�B�������Ă͂�
���܂���v
�������A���C�����Ɍ��������t�͂���1�T�Ԍ�A�S������ŖS���Ȃ����B�_���͉��t�Ƌ��ɏ�
���A���ɖ���邱�Ƃ͂Ȃ������B�}�L�ɂ͂��ꂪ�c�O�������B
������"����"�Ƃ������t���g���̂͂�߂悤�Ǝv�����B���t���������킩���Ă���A�s
��������Ă�����������Ȃ��B��낤�Ǝv���Ă��邱�Ƃ́A�����ɒ��肵�悤�A������
���Ɛ������B���e�𑁂��S�������}�L�ɂƂ��āA���t���e���肾�����̂��낤�B
����݂�Ƃ�������q�Ɍ������ă}�L�͔��B
�u����q�A�l���ň�ԓ�����Ƃ͉����킩��H�v
�u�����A�Ȃ�ł��傤�v
�u���ɕ���B����͎����ł͌��߂��Ȃ��B����ɒN�ɂ��������Ȃ��v
����q�͍l�����B
�u�������w��͌×��̌��l�E�̐l�̋�������A�����̐������܂ŎR�قǂ��邯�ǁA���ɕ���
��������̂͂Ȃ��̂�B���E�͖��O������ˁv
���ɕ��ł����ƍl�����ނ���q�ɁA�P�C���A�܂��n�܂����Ƃ�����œ��ۂ݂�Еt���n��
���B
�u�����āA����ŋA���Ă����l�͂��Ȃ��̂����́B�Վ��̌��ł��Ԕ��������l�͂�������
�Ă��A��������ɂ܂ōs�����l�͂��Ȃ��̂�v
����͂����ł����ǂƁA����q�͘r��g�B
�u�r�f�b��"���ʂ܂Ō��C"�������t������ǁA����͋C�����̖��Ȃ̂�B����̒��ɂ͈�
���O���̈ꂵ���Ȃ��l�����邵�A���a��������l������B�����炱���A�����悤�A����
��ɂ��悤�Ǝv���Ă���킯�v
�˘f������q�ɁA�g���̗p�ӂ����Ă����P�C�������D���o�����B
�u����q����A�o����̘b���܂��߂ɍl�����Ⴞ�߂�B�������������Ȃ��Ă��܂�����A��
��������ɕ��������Ƃ��������v
�@�P�C�͂��̘b��ɊW�����āA�g���Ƌ��ɃX�R�[�������߂��B
�@�ق��ق��̃X�R�[���ɃC�`�S�W������h��ƁA�C�M���X�̃A�t�^�k�[���e�B�̂悤�ȋC��
�ɂȂ��B�ڂ̑O�̃v���X���[���ǂ��̃S�[���h�̃W�����v�X�[�c�𒅂��}�L�ƁA���ɕ���
�_����}�L�A�ǂ�����}�L���B�����āA�X�R�[�����Ƃт��肨�������̂������B
�u�Ƃ���ŁA�v���X���[�͂܂������Ă����ł����v
�}�L�͂����ƃX�R�[�����A�ɋl�߁A�P�C�͂Ղ��Ɛ����o�����B3�l�Ŋ�������킹�Ďv����
�����B
�u�o����A�ǂ��ł��������Ƃ���ŁA�̐S�̂��Ƃ͂��b���ĂȂ��ł���v
�@�P�C�̌��t�ɂ���q�́A�܂���������̂����b�����B
�u����q����̍u���̂��Ƃ�b�����͎̂o�����ǁA���������͉���̕��̈�˒[��c�Ȃ́v
�@�����1�l���A�����t�B�X�s���̃g�����N�I�т̘b����A���鏗�D�̘b�������B
�e���r�Ŋҗ���߂������D���A���̐��Ƃ�������鎞�ɂ́A�g�̉��̕i�̓g�����N1��
�炢�ɂ��Ă��������Ɣ����������ƂɎn�܂�B
�@���̂��ƂŁA�^���h�ƁA�Ȃɂ������܂Ŕh�ƁA��̂��ƂȂǒm��Ȃ��h��3�ɕ����ꂽ�B
�^���h�͂������A�g�����N1�܂ʼnו������炷���Ƃ�ǂ��Ƃ����B�Ȃɂ������܂Ŕh�́A
���݂̉ו������炷���Ƃ��l�������ł悢�̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӌ��������B
��̂��ƂȂǒm��Ȃ��h�́A���������Ȃ��Ȃ�����N�������Ƃ����邾�낤����A�]�v�ȐS
�z�͂��Ȃ��̂��������B���̔h�͉Ƒ��Ɠ����������A�^���h��1�l��炵�����������B
�u����Ȏ�����A�Еt���Ȃ�����Ƃ����b�ɂȂ����́B�����ł���q�̎����v���o���āB��
�����̗F�l�ɂ��������u�������Ă���l�����܂����ďЉ���̂�����ǁc�v
�u���A���܂ŁA�i�C�A�K���̑�̂悤�ȃt�@�b�N�X�����܂����v
����q�̔���̓}�L�ɂ͒ʂ��Ȃ��B
�u�Ƃɂ����A�����@��Ǝv���̂�ˁB���C�N��p�[�\�i���J���[�̍u���������ł���B
����̐l�������y���݂ɂ��Ă��邩��A��낵���ˁv
�@�y�Y�ɂƁA�P�C�����n���ꂽ���܂ɂ̓X�R�[���������Ă����B
�@�������ɖ߂�ƁA�܂�݂��d�b���������B
�u�u���̓��������܂�����A�P�C������̕������ɘA�����Ă����́v
����𑁂������Ăق��������ƁA�܂�݂͂ӂ��ꂽ�B
�u�P�C���炨�y�Y��������Ă����̂�����ǁc�v
����q�͂܂�݂̑O�Ŏ��܂��Ԃ�Ԃ炳�����B
�r�[�ɁA�܂�݂̕\��^���ɂȂ�A�@�̌����҂��҂��Ƃӂ���܂����B
�u����͏Ă����ẴV�t�H���P�[�L���N�b�L�[�̂ɂ����v
�u�X�R�[���Ł[���v
����q�������I���Ȃ������ɁA�܂�݂͎��܂��Ђ��������āA�����̗p�ӂ����ɑ䏊�֏�
�����B�@�@�@�@
�@3������B
SGC�̉�������́w�킭�킭�ЂÂ��u���x���J�Â���ɂ�����A����q�̓P�C�ɑ��k�����B
���O�ɃA���P�[�g���Ƃ��Ă��炢�A�u�g�����N1�h�v�u�Ȃɂ������܂Ŕh�v�u��̂��Ƃ͒m
��Ȃ��h�v�ׂ��B
�@��������Ȃ���܂�݂��v�Z���A�����B
�u�g�����N�h�v��1���A�u�����܂Ŕh�v��7���A�u�m��Ȃ��h�v��2���ł��B
�@�X�R�[���ɂ��Ԃ���Ă���܂�݂̑O�ŁA�A�[���O���C�̍g�������݂Ȃ��炭��q��
SGC�̃����t�B�X���s����n�܂����A�g�����N1�̂���������b�����B
�u�Ȃ�قǁA���y�̗��ɂ̓g�����N1�ł����v
�u�ӂށA�������Ė������ǁc�܂�݂����A�ŋߔ��Ă�݂����ˁv
�u�͂��A���낢��ƖZ�������̂Łv
�u�}�L��������l���炢�G���r�X�̃c�A�[�ɎQ���ł�����Ă���������Ă����ǁv
�u�����A���������ďo�������ł����H�v
�u�������A����ł��v
���[���A����ς�ƁA�܂�݂͍Ō�̃X�R�[���ɂ��Ԃ�����B
�u����q����A�ЂƂ킩��Ȃ��̂ł����v�܂�݂������������
�u�m��Ȃ��h�́A�ʂɕЂÂ��Ȃ�ċC�ɂ��ĂȂ��̂ɁA�Ȃ����̍u���ɎQ������̂ł����v
�u����͂킽���̐��������ǁA���ɁA�F���Q�����邩��Q���������B�����͈�˒[��c��
�����Ȃ��̂����v
�u���Ȃ��ƁA�ǂ�Ȉ����������邩�킩��Ȃ��I�@�ł����v
�u����͋ɒ[�Șb�����ǁB���ɁA�ЂÂ��͋C�ɂ��Ȃ��ƌ����Ȃ�����A�ǂ����ŋC�ɂȂ�
����v
�u�m���ɁA������������܂���ˁv
�u����ɁA����Ȃ��Ƃ��l�������Ƃ��Ȃ������l���A�w�g�����N1�x�̘b�ŁA�ӎ����ς��
��������Ȃ����ˁB�����ŁA����3�̔h���e�O���[�v�ɐU�蕪���Ă��傤�����v
�u�����v
�@�r�f�b�̉�������u�킭�킭�Еt���u���v�́A��10������[��4���܂ł�1���u���ł���B
7�`8�ŃO���[�v�ɂȂ�A���K������B
�@�ߑO���́A���C�N��p�[�\�i���J���[�ŁA�Ȃ肽�������̃C���[�W�����߂�B
�u���ň�Ԑ���オ��̂͂��̎��Ԃł���B���݂��ɔ�]���Ȃ���A����`������j�g��h
��̂́A�j���ɂ͂킩��Ȃ��y���݂ł��낤�B
�܂��A�V���v�����C�t��W�Ԃ��A�����f�b�s���蕨�ɂ��Ă��鏗�����A�F�ɂ���ȋ@
��ɗV��ł݂���ƗU���A�������C�N������Ɗ�F���ǂ��Ȃ�A�Ⴍ������ƌ����Ă�
��ł��Ȃ��l�q�ł���B
�@�p�[�\�i���J���[�Ŏ������F��f�f�����ƁA����ł��̔�₵��������Ȃ��Ƃ킩
��������v�����ď����ł���Ƃ����������������B
�u��͒m��Ȃ��h�v�͓̉����~�́A������Ȃ����͒u���Ă����ΒN�������邾�낤����A��
�����邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�ɂ˂ƁA�C�y�ɑ���K�b�ɘb���������B
�u�N�����āA�N�ł����H�v
�K�b�̖₢�ɖ��~�͌����������B
�u���A����Ⴀ�c�Ƒ������邩��c���Ƃ��v
�u������Ɨm���̃T�C�Y�͓����ł����v
�u���͂킽�����w����������c�̏d�͂킽���̕������邯�ǁv
����ł́A�����ł��˂ƌ����K�b�̌��t�ɖ��~�͂ނ��ɂȂ����B
�u�܂��A���̓_���ł��A�������邩��̌^�͎����悤�Ȃ��̂����v
�u�m���̍D�݂͎��Ă��܂����v
�u�Ⴂ�܂���B���͒��N����������������c�v
�u��������A�N�����~����̗m���𒅂�l�͂��Ȃ��̂ł́c�v
�Ղ�悤�ɖ��~�̐��������Ȃ����B
�u�ȁA��Ɋ�t����Ƃ��A���낢�날�邶��Ȃ��́v
�u�N������Ɋ�t����̂ł����v
����͂ƁA���~�͉����������B
�u����Ȃɂ����߂Ȃ��Ă��A������Ȃ��́B���~���m���𗭂߂���ŁA�R�قǂ̃S
�~���c���Ă��̐��ɍs�������ĉƑ������邾���ŁA�킽�������ɂ͊W�Ȃ��̂�����v�ƋP
���������͂��ށB
���Ȃ�������̋P�����������t���ʂŁA���~�̊�F���ς�����B
�u�P������A�킽���̗m�����S�~�����肾�Ƃ����́v
�����A�Ȃɂ�����Ȃ��Ƃ́A�˂��A�F����Ƃ��남�낵�Ȃ��瓯�ӂ����߂����A���ʂ���
���B
�u���̓S�~�łȂ��Ă��A������S�~�ɂȂ�Ƃ������Ƃ�v
�K�b�̋��������ɁA���~�͕@���������Ă���B
�C�܂������͋C�̃e�[�u���Ɂu���ꂩ�烉���`�^�C���ł����������ٓ������z�肵�܁[���v
�Ƃ����P�C�̐����Ђт����B
�@����Ƃ͕ʂ̃e�[�u���ɍ����Ă���܂�݂́A�ڂ̑O�̖��̓��ٓ��̂ӂ����J���Ȃ��炤
�ꂵ�������B
�u�z�e���̉����ōu��������ƁA���ȃ����`���H�ׂ��čK���ł��v
�u�����˂��A100�l������ŁA�H���̒��ł���Ƃ���ƌ����ƃz�e�������Ȃ��ł���
���˂��B��������Ɋ܂܂�Ă��邩��v
�@�P�C�͐H���������킽���Ă��邩�ǂ������ĉ���Ă���A�}�L�͂ǂ����̃e�[�u���Řb��
����ł���B�܂�݂͔��̐�̐l�Q�����Ȃ���A�����₢���B
�u����Ȕ~�̌`�ɐ����l�Q���v���Ԃ�Ɍ��܂����v
�u�a�H�͖������łȂ��A�ڂŌ��Ĕ������̂��d�v�ȗv�f������B���������ƌ�����������
�����ǁc�v
�@2�l���̂ɐl�Q�̘b�����Ă��鍠�A���~�̃e�[�u���ł͂܂����Ă��S�~��肪�����Ԃ�
������B
�u�������̘b�ł����ǁA�킽���̗m�����S�~�Ȃ�A�P�������K�b����̗m���̓S�~�����
���̂ł����v
�P���������悤�Ƃ���̂𐧂��āA�K�b���ق��Ƃ��Ȃ����ƌ������B
�u�ق��Ƃ��Ȃ����Ƃ͂ǂ��������Ƃ�v
���~�͔���u���ė����オ�����B
�u���͐H���̎��Ԃł���v�K�b�͖��~�����Ĕ��������B
�u�킽���̗m�����S�~�ƌ���ꂽ�܂܂ł́A�H�����̂ǂɒʂ�Ȃ��v
�u����Ȃ�H�ׂȂ��Ⴂ���̂�B�_�C�G�b�g�ɂȂ��Ă��������B�ӂӂ�v
�u�킩��܂����v�Ɩ��~�͂��܂肱�B
���~�ƍK�b�̊Ԃɂ͋P�������S�n�������ɍ����Ă���B���~�͐Ȃ��ڂ낤�Ƃ��ĕٓ�������
�グ���B�P�����~�߂悤�Ƃ��Ď���o�����̂��܂��������B���~�̓o�����X������A�P����
���ɗ������Ԃ��܂���ꂽ�B
������A�L���b�A���[���A����ȁA���܂��܂Ȑ���������A���~�͂ڂ�����Ƃ��ė����Ă�
��B�P��������U��ƁA�����Ȕ~�����ƍ��쓤�������ɔ�B
�@�P�C���f�����s�������B
�u�P������A���ώ��ɍs���܂��傤�B����q����͖��~������e�B�[���[���ɂ��A�ꂵ�Ă�
�������B���̕��X�͂��H���𑱂��Ă��������ˁv
�@����������ɁA�}�L���}�C�N�ł��Â��ɁA�H���̌�ɂ̓R�[�q�[���g�����o�܂��ƈ�
�������B���r�[�̉��̃e�B�[���[���Ń~���N�e�B�[�Ƀu���E���V���K�[���O����āA�X�v
�[���ł�����肩���Ă��関�~�͖ڂɗ܂��ׂĂ����B
����q���R�[�q�[�����݂Ȃ���A���~�̌��t��҂����B�X���ɂ̓s�A�m�̋Ȃ�����Ă����B
�u�P������ɁA����Ȃ��Ƃ����Ă��܂��āA�킽���c�v
�u�Ȃɂ��������̂ł����v
�@���~�͎����̗m�����S�~���ƌ����ĕ��������Ă����Ƃ������Ƃ�b�����B
�u�m���͂킽���ɂƂ��đ�ȕ��ł��B������c�v
�@
�@���~�̕�͗m�ق����ӂŃ����s�[�X��R�[�g�܂Ŏd���ĂĂ��ꂽ�B���~�Ɏ������݂̌`��
���C���͂������l�ɂق߂�ꂽ�B�ꂪ�S���Ȃ��Ă��A�m�������͂��̌`�ɂ������
���B
�u�킽���́A���ł��m���ŕ�ƂȂ����Ă���̂ł��v
�u�K�b����́A���̂悤�Ȃ�������������łȂ������ł��傤�ˁv
���~�͂�����������A�܂𗬂��Ă��Ⴍ�肠���Ȃ���Ԃ₢���B
�u����Ȃ��Ƃ����āA�킽���͂������̉�ɂ͎Q���ł��Ȃ��Ȃ�܂��ˁv
�u����Ȃ��Ƃ͂���܂����B�P��������킩���Ă�������Ǝv���܂���v
�����ł��傤���ƁA���~�͂���q����ڌ����Ɍ����B
�u���������A�݂Ȃ�����킩���Ă�������Ǝv���܂���B���̍u���Ńp�[�\�i���J��
�[��������Ă���̂́A��ɂ͗m���̏��������₷�����邱�ƂȂ̂ł��B�����͂Ȃ���
���m���������ł��Ȃ��̂ŁA�������F��������A������Ȃ��F�̗m���ɕʂ�������₷��
�Ȃ邩�Ǝv���܂��āB��ڂ́A����̗m���I�т̂��Q�l�Ƃ����Ӗ��ł����v
�u���������Ȃ̂ł��v
�@
�@����q�́A���~��"�����̎������F"�ɕs���Ȃ̂��Ǝv�����B
���������ƃo�b�O�̒�����"�����̎������F"�̃J���[�T���v�������o�����~�͏����F�̃W
���P�b�g�ɏd�˂��B
�u�ق�A���̐F�Ǝ������Ă��镞�ƁA�قƂ�Ǔ����F�ł��傤�v
����q�͂��Ȃ�����
�u�m���̃f�U�C�����ł����A�F���A���Ɏ������F�͂��̐F�Ƃ��̐F�Ƃ������ɁA��͋�����
����Ă����̂ł��v
�u�����玗�����F�̗m���������Ă����Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁv
�u�����ł��B������A�]�v�̂Ă��Ȃ��v
����q�͘r��g��ōl�����B
�u���~����A���ꂳ�܂��c���ꂽ�̂͗m���ł��傤���B����Ƃ����~����̌����ɂ�
�Ȃ����Ƃ������Ƃł��傤���v
����q�̌��t�͖��~�ɂ͈ӊO�������炵���A�꒷�̖ڂ����J�����B
�u���H�v
�u�����ł��B���~����炵���������o���ɂ́A���̐F�ŁA���̃��C���ƍl���Ă���ꂽ�̂�
���傤�ˁv
�u�킽���炵���H�v
����q���������B���~�̕ꂪ�c�����̂͗m���ł͂Ȃ��A�P���Đ����ė~�����Ɗ肤��̎v��
�������̂ł͂Ȃ����낤���B
��߂��g�������݂ق��āA���~�͋������B
�u������x�A�������l���Ă݂܂��B����ɋP�������c�K�b����ɂ��c�ӂ�܂��v
2�l���e�[�u���ɖ߂�ƁA�P�����Ί�ŐȂɂ��Ă����B
�u��������Ȃ����v
�v�������Ȃ��K�b�̌��t�ɖ��~�̐����k�����B
�u�P������A�K�b����A�݂Ȃ��߂�Ȃ����v
�@�ߌ�̍u���͂Ȃ��₩�ɐi�B
�@3���̃R�[�q�[�^�C���ɁA���~�͗����オ���āA�e�[�u���̈�l�ЂƂ�̊�����Ă��肪��
���������܂����Ɠ����������B
�u�Ȃɂ����Ă܂��ǁA�Ȃ�̂���ł����v�ƍK�b���q�˂��B
�u�����A������ł��B���炪�����������������Ȃ̂Łv
�@���~�̏Ί�ɊF�͊�������킹���B�ꂪ�����Ă��ꂽ�̂́A�����炵���P���Đ����邱��
�ł����āA�m���߂��ނ��Ƃł͂Ȃ������̂��ƋC�t�����Ă��ꂽ���ӂ̋C�����������B
�g�����N1�Ƃ͂����Ȃ��܂ł��A��̎v���o�Ƃ������m�Ɏ�������̂ł͂Ȃ��A���ꂩ���
�����ɖڂ����������Ǝv�����B
�u�Ƃ���ŁA�K�b����̓g�����N��ɉ����l�߂�̂ł����v
�ˑR�̖₢�ɍK�b���S�O�����ɓ������B
�u�v���o�Ɗ��Ӂv
�F�̎肪�~�܂����B
�u�킽���A���Ȃ́v
���߂�Ȃ����B����Ȏ��Ƃ́c���~�͐�債���B
�K�b�͎��U�����B
�u�����̂�B�C�ɂ��Ȃ��ŁB�������x�����̈Ⴂ������v
�@���~�͍����̂��ƁA�K�b�̂��Ƃ�Y��Ȃ��ł������Ǝv�����B
 �@
�@
��܂���ł����B���������悤���Ǝv���܂������A10�N�ЂƐ̂Ő��̒��̕ω���`����Ӗ�
�ŁA�����͂��̂܂܂ɂ��Ă����܂����B
���̒��ɏo�Ă���u�g�����N1�v�Ƃ�������������D����́A2018�N�ɖS���Ȃ������؊�
�т���̂��Ƃł��B�e���r�h���}�́u�����ё��Y��Ɓv�̍��́A�ʔ��������Ǝv���A���̌�
�͋H�L�ȍ˔\�̕����Ǝv���Ă��܂����B����
2018�N9��17���u���O�@���ߏ��̉ԉ��Ɓu�I�t�B�[���A�v�@�ɂ������Ă��܂��B
�@ �@
�@
�@�u���炵����v�i�g�o�Q�j�@���ē��@
�@

 |
 |
||||
 |
 |
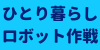 |
�@�u���炵����v�i�g�o�P�j�@���ē��@
 �g�o�P�w�@�@�@ �@�@
�g�o�P�w�@�@�@ �@�@�@�@
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
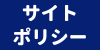 |
 |
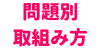 |
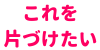 |
�@
�@���u�V�O�����v��(���j���炵������o�^���W�ł��B���f�ł̏��p���p�͂��f�肵�܂��B