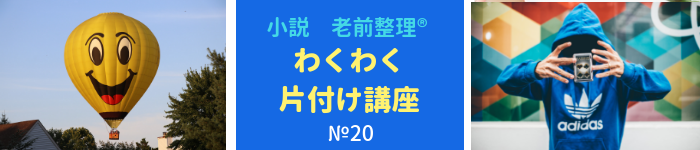老前整理 片付け 整理 終活 シニア 行動経済学 ひとり暮らし ロボット
20 、サポーター殺人事件(3)
サポーターになりたい動機もさまざまで
「自分は、この20年ものを捨てたことがありませんでした」
うそぉー、そんなバカなという声がささやかれた。
坂根は四角い銀縁のメガネの端を指で押し上げて、その人差し指を目の前で左右に振っ
た。
「うそではありません。20年会社に、いえ、実は警察に勤めていましたが、両親が交通事故
であっけなく逝き、仕事が虚しくなって退職しました。その後は残された小さな畑で晴耕雨
読の生活です。生ごみは土に返して堆肥にしますし、そんなに簡単にものを捨ててはいけな
いと思っていました。壊れた電気製品も納屋にしまってあったし、両親のものも全部その
ままでした。ところが本がいけない。本棚どころか、階段、廊下は言うに及ばず、台所にま
であふれてしまいとうとう床が抜けました」
坂根は情けなそうな顔でまたメガネを持ち上げた。
「大工さんに来てもらうと、これだけの本を収納できるようにするためには、土台からやり
直さなければいけない。つまり家を建て直さなければ無理だと言われました」
坂根は口をゆがめて苦しそうに心情を語った。
「大工さんに、ところで坂根さん、この古本とガラクタのために家を建て直すのと、本を処
分して床を直すのとどちらにしますかと聞かれました。わたしはこのことで胃潰瘍になるほ
ど悩みました。そして決心したのです。愛しい本を処分しようと。ところが何から手をつけ
ていいかわからないし途方に暮れていると、様子を見に来た大工さんが、これに行ってはど
うかとチラシをくれました。それがこの片付け講座のものでした」
「本を処分することは、わたしにとってとてもつらいことでした。まるで血や肉を削られる
ような気がして、心が悲鳴をあげました。しかし男が一度決めたからにはと思い直したので
す。ところがくら子さんの紹介で、ぽんぽん堂の恵比寿さんに本を持って行ってもらうと、
さびしくなるどころか、妙にすっきりして気持ちがよいのです。はじめは半信半疑でした
が、少しずつ片付けているうちに捨てることが楽しくなって、加速度的にものが減って納屋
のがらくたもなくなり、まるでつきものが落ちた感じでした。がらんとした納屋で何かでき
ないかと考え、古い樽に畑の白菜を漬けることにしました。亡くなった母は白菜の漬物が得
意で、昆布やリンゴの皮など色々と工夫して入れてたのを思い出して、作ってみたのです。
これを大工さんにお礼に差し上げると、おいしいとほめられたので、あちこちに持って行く
と、また、うまい、うまいで評判になりまして、今は本を読む代わりに漬物を漬けていま
す。実は老眼が進んで、小さな文字の本を読むのもつらくなってきたので、ははは」
坂根は目を細めた。
「自分にこんな新しい道が開けるとは思いもしませんでした。新聞によるとこれから男のひ
とり暮らしや無縁死が増えるそうですね。それでわたしのような人間も多いのかもしれない
と思い、何かお役に立てればと思った次第です。以上」
拍手と共に白菜の漬物が食べたいという声が起こり、坂根は来週持って来ますと、はにか
んで答えた。
「次回は弁当箱に、ご飯を詰めてこようかなぁ」
まろみのつぶやきに、くら子は呆れた。
次は宮本和美だった。
「なんだか皆さんすごい方ばかりで、ふつうの主婦のわたしが参加して良かったのかと思っ
ています。それに皆さんのようにうまくしゃべれないし」
和美は困ったような顔をして、唇を結んだ。
「でも、わたしのようなものでもサポートのお仕事ができるようになれば」
声が震えて、先が続かなかった。
元アナウンサーの串本あずさが助け船を出した。
「誰でも同じですよ。わたしも始めは人前でしゃべるのがこわかったんですよ」
ほんとに? と、和美はあずさをすがるような目で見た。あずさはこくりとうなずいた。
「きっと、自己紹介があると練習してきたのですけど、頭が真っ白になって」
車いすの町田栄津がもう一度はじめからやってみたら? と提案した。
くら子もうなずいたので和美は目をつぶって深呼吸をし、一礼してから自己紹介を始めた。
「わたしが『わくわく片付け講座』に参加したのは、母の遺品整理をして娘にこんな思いを
させたくないと思ったからです。だから、今のうちに身の回りを片付けようと思いました。
短大を卒業し、3年勤めて夫と職場結婚をしてから、ずっと主婦業でした。娘たちも嫁にい
き、ほっとしたところに鳥取の母が倒れ、遠距離介護が始まりました。父はわたしが高校の
時に亡くなり、母が女手一つで妹とわたしを育ててくれました。だから、離れてはいても、
できるだけのことをしたいと思い、高速バスで介護に通いました。しかし2年で母も逝き、そ
の後が大変でした。田舎の古い家で、坂根さんのところと同じように何もかも取ってありま
した。わたしの三輪車からフラフープ、だっこちゃんのしぼんだ人形までありました。あれ
って子どものころに流行ってたんですよね」
まあ、懐かしいという声に重なるように、わたしも遊んだという弾んだ声があがった。
「良かった。やはり同世代の方々には通じるんですね」
和美が微笑むと、頬にくっきり二つのえくぼが浮かんだ。
はじめの緊張はどこへやらで、宮本和美は自己紹介を終え、拍手に包まれて頬を染めた。
次は、竜崎貴美香だった。
「わたしはあるNPOに参加して、傾聴ボランティアを始めたのですが、3ヶ月でクビになり
ましたぁ」
貴美香は手刀で自分の首に手を当ててのけぞった。深刻な話なのだが、貴美香のコミカルな
動きに笑いが起こった。
「なぜクビになったかといえば、訪問先のおばあちゃんに着物をもらったからですぅ。物欲
しげにしたり、ちょうだいちょうだいとねだった訳ではありませーん。おばあちゃんが何度
もこの着物を持って帰って着てちょうだいとおっしゃるのですぅ。だからぁ、断るのも辛く
なって、それではともらって帰りました。NPOではものをもらっちゃいけないと言われてた
んですけどね。おばあちゃんがこんなに言うんだから、ま、いいかと思って。ところがぁ」
貴美香は頭をぐるっと回して足を踏み出し、両手を広げ歌舞伎のように見得をきった。
「よっ、竜崎や」とコーケンこと佐伯弘憲が声をかけた。
笑顔で片手をあげて貴美香はコーケンに、ありがとさんと答え姿勢を戻した。
「着物をもらってから、そのおうちに行く度にあの着物はどうしたかとおばあちゃんが聞く
んです。何度も何度も。でもねボケてるわけではないんですよ。頭はしっかりしてました。
そのうえご近所に、高価な着物をボランティアさんにあげたと吹聴して回って。そんな風に
言われるとは思ってもみなかったし、うっとおしくなって、着物を返そうと思ったらそのこ
とがNPOの理事の耳に入って、ボランティアの風上にも置けないって、ジ・エンド」
貴美香は涙をぬぐう真似をしてひどい話でしょうと訴えたがうなずくものもあれば、首をか
しげる者もいた。
「そりゃあ、規則に反しておばあちゃんに着物をもらったけど、その方がおばあちゃんが喜
ぶと思ったからなんです。それでわかったのは、人間は年をとるとすごーくものに執着する
ようになる。だから一度人にあげたものでも、惜しくてたまらなくなるんです」
反論しますと司法書士の村上弘江が手を挙げた。
「確かに、そういうケースもあると思いますが、人にもよります。先日わたしに遺言書の作
成を依頼された方は88歳の女性でした。子どもさんに先立たれて身寄りがないので、遺産は
すべてある団体に寄付してほしいということでした。そういう人もおられますので、お年寄
り全体を非難するような言い方は慎んでいただきたいと思います」
有無を言わさぬ口調だった。そんなこといわれてもぉと、貴美香はふてくされた。
ヴィクトリア女王を気取る仙波克枝は、真顔で聞いた。
「それで、そのおばあちゃんの高価な着物はどうなったのでしょうか」
は? 着物ですかと貴美香は首をかしげた。
「もちろん、そのままうちにありますよ」
持ち時間終了のチリンが鳴った。
「どうしておばあちゃんに着物を返さなかったのですか」
克枝は合図などお構いなしに詰問した。
「そりゃあ、NPOをクビになったから…」貴美香は天井を向いて答えた。
大山が手を挙げた。
「着物より、ケイチョーってなんですか。こちとら、慶長というと徳川時代の慶長小判の慶
長しか知りませんが、小判は関係なさそうだし…」
腕を組んで、大山は額に皺を寄せた。
「えーっ、わたしは慶弔ってよろこびごとやとむらいのことだと思ってたので、ボランティ
アで葬儀の手伝いでもするのかと思ってました」
元動物探偵の陸奥慶子も知らなかったようだ。
まあまあと、有料老人ホームで相談員をしている栄津が割って入った。
「傾聴というのは傾は傾ける、聴は耳へんの聴くという字を書きます」
くら子が立ちあがってホワイトボードに傾聴と書いた。
「くら子さん、ありがとうございます。ええとそれで意味はですね、相手の話にじっくり耳
を傾けること。高齢の方は話し相手がなかったりすることも多いので、そういう方のお話を
聞くことです。そうですね貴美香さん」
貴美香はこっくりうなずいた。
「聞くだけ? そんなボランティアがあるのですか」
経理一筋の梅森も思わず発言した。
貴美香が答える前に、栄津がそうです。ただと言葉を濁した。微妙な空気を察した元アナ
ウンサーの串本あずさが、次の方が待っておられるのではないでしょうかとくら子を見た。
貴美香がボランティアをクビになったということはわかったが、なぜこの講座に参加したの
かはわからなかった。しかし確かにあずさの言う通り、順番を待つ身にすればつらいであろ
う。人前でしゃべることが苦手な人や、自己紹介が嫌いな人は前の人が早く終わらないかと
じりじりし、他の人の話を聞くにも身が入らないだろう。
「そうですね。傾聴の話はまた改めてということで」
くら子は次の明田輝を促した。
「姓は明るい田んぼの明田です。名前は…」
明田はホワイトボードに「明田輝」と書いた。
「これを見ると、明日輝くになるのですが、あきらと読みます。祖父がふざけた名前を付け
てくれたもので、子供時代はからかわれましたが、仕事をするようになると一度で覚えても
らえるいい名前で、縁起がいいともいわれ気に入っています」
グレイの背広にえんじの地に白い水玉のネクタイを締めた明田は、よく通る低い声で続け
た。
「仕事は脱サラして、ハウスクリーニングの会社を経営しています。というと聞こえはいい
ですが、お掃除おばちゃんを派遣している小さな会社です」
村上弘江が、おばちゃん? と、明田をにらみつけた。
いや、失礼、と明田は軽く手を挙げた。
「すばらしい熟女たちですな」
この発言で女性陣の目はますます厳しくなった。
「それで、まあ、熟女たちに頑張っていただいているのですが、皆さん忙しいのかいわゆる
汚部屋なるものが出現しまして、これは掃除以前の問題でありまして、お掃除おば…いえ、
女性たちも困っております。ものをどけないと掃除ができないのですが、それがもう。いや
はや、なんとも想像を絶する状態でして、そこで考えた末、汚部屋の片付けのプロを養成し
ようと思いましたが、ノウハウがないのでわたしがこちらで勉強して、教育をしようと思っ
ている次第です」
まろみがくら子にささやいた。
「明田さんの受講の動機に、そんなこと書いてありましたっけ?」
くら子は無言で首を振った。
明田は自分が社長としていかに努力しているか、どれほどパートの人たちに気を使ってい
るかを熱弁した。
終了の合図のチリンが鳴ると、明田はあとひとことと早口でまくしたてた。
「わたしはわが社を日本一の会社にしたいと思って、一生懸命頑張る所存です」
「勝手に頑張れば」と村上弘江が吐き捨てるようにひとりごちた。
「女性をたくさん使っていると、井戸端会議でいろいろ言われるもので耳さとくなりまして
な」
明田はにやにやしながら村上を見た。
「では、はっきり申し上げます。わたくしの経験から言わせてもらえば、女性をバカにして
いる経営者で成功した人を見たことはありません」
なに! 明田の表情が一瞬にして変わった。
「お前は自分を何さまだと思ってるんだ」
「あんたこそ、何さまよ」
険悪な空気が漂ったその時、明田の携帯電話が鳴りだした。
講座を終えて、後片付けをしながらまろみがくら子に聞いた。
「明田さんの着メロがウケてましたけど、鉄人なんとかって、なんですか」
手を止めて、くら子は笑いながら答えた。
「鉄人28号よ。昔流行った漫画の主題歌。ビルの街にガオーではじまるの」
「はぁ、鉄人ですか」
「料理の鉄人じゃないわよ。鉄でできたロボットで、鉄人28号」
明田の着メロにささくれだった雰囲気が変わり、皆がなつかしいと微笑んだ。
当の明田は携帯切るのを忘れてた、ちょっと失礼とあたふたしながら部屋を出て行った。
明田にきつい言葉を投げつけた村上も、相手がいなくなっては何も言えない。
大山と坂根は、鉄人28号のロボットを持っていたと胸を張った。梅森とコーケンは、漫画
で読んでいたと負けん気をみせた。
「わたしはバービーやタミ―ちゃんで、遊びました」
貴美香の言葉に、女性たちは妹がうらやましかったとか、田舎にはなかったとか、話題には
事欠かなかった。明田が席に戻った時には、次の自己紹介が和やかに始まっていた。
「ほんと、あの時はジェネレーションギャップを感じました」
まろみは情けなそうにくら子を見た。
「まだ生まれてなかったのだから仕方がないわよ」
「でも、明田さんと村上さんのにらみ合いはこわかったです。つかみあいのケンカになるん
じゃないかと思いましたが、鉄人28号に助けられましたね」
ハハハお陰で無事終了いたしましたと、くら子は最後の椅子を片付けた。
「しかし皆さんすごいエネルギーですよね。部屋が熱気でムンムンしてました」
バッグを肩にかけて、まろみはがらんとした部屋を見回した。
「そうねえ、それくらいでないとサポーターはできないわね」
エレベーターの中でまろみは聞いた。
「全員がサポーターになれると思いますか」
「それはわからない。もちろん資質もあるけれど、結局はやる気かな」
「そういえば、宮本和美さんは自信がなさそうでしたね」
「話し方は練習すればなんとかなるし、うまくしゃべれればいいというものでもないのよ」
「ただ、皆さんには強みがある」
「なーるほど」
基本的に「わくわく片づけ講座」に参加する人は片付かない人である。
講座に参加して考え、悩みながらモノの要不要を考え、行動した人たちである。これは一つ
の成功体験になる。
例えば、近所の散歩しかしていなかった人が、標高千メートルのあの山に登りたいと思い、
準備をして少しずつ登っていく。途中で休憩したり、ため息をつくことがあっても、頂上に
たどり着けば、目の前には今までに見た事のない新しい風景が広がる。この感動と風景を誰
かに伝えたいと思った時に、サポーター講座への道が開けるのかもしれない。また片付けた
いと言いながら、挫折したり、進まないのは片付けを目的にしているからかもしれない。
目的と目標の違いについて考えてみると、例えば本に載っているおいしいケーキが食べたい
と思った時に材料を買って準備をしてケーキを作る。この場合、ケーキを作るのが目的では
なく食べるのが目的で、そのためにレシピ通りのおいしいケーキを作ることが目標になる。
くら子とまろみは事務所への帰り道、今日の講座を振り返った。
「ほんと、多彩な人たちが集まってくださったわね」
「そうですね、動物探偵には笑いましたけど。そうそう、あのヴィクトリア女王は喰わせ者
ですよ。夫の喪中だからという黒ずくめの衣装も嘘っぱち」
まろみの言葉が険しくなった。
「もしかしたら、克枝さんは女優さんなのかも」
はあ? と、まろみは気の抜けた声をもらした。
「そんなこと言ってませんでしたよ。あの人なら真っ先に言いそうじゃないですか」
赤信号でくら子とまろみは立ち止った。
サポーター殺人事件(4)に続く
を考えていたのだなと思います。
今回の話に成年後見の話が出てきますが、先日(2019年2月16日)奈良県宇陀市の成年後見
シンポジウムで「転ばぬ先の老前整理」の講演をさせて頂きました。
少しは現実とつながってきたかなと思っています。
「くらしかる」(HP2) ご案内 

 |
 |
||||
 |
 |
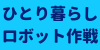 |
「くらしかる」(HP1) ご案内 
 HP1ヘ
HP1ヘ  |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
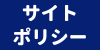 |
 |
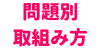 |
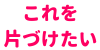 |
◆「老前整理」は(株)くらしかるの登録商標です。無断での商用利用はお断りします。