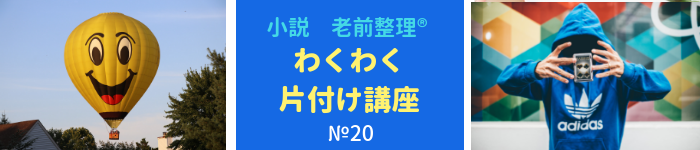کV‘Oگ®—پ@•ذ•t‚¯پ@گ®—پ@ڈIٹˆپ@ƒVƒjƒAپ@چs“®Œoچدٹwپ@‚ذ‚ئ‚è•é‚炵پ@ƒچƒ{ƒbƒg
20 پAƒTƒ|پ[ƒ^پ[ژEگlژ–Œڈپi‚Pپj
پ@•ذ•t‚¯ƒTƒ|پ[ƒ^پ[چuچہ‚ًٹJچu‚·‚é‚ئپAƒXƒpƒC‚ة•غŒ¯‹àژEگl‚ئپc
پ@پ@پ@
پ@
پ@‚ـ‚ë‚ف‚حˆؤ“à‚ً‘—‚ء‚ؤ‚©‚çˆêڈTٹش‚إ“ح‚¢‚½گ\چڈ‘‚ً‚ـ‚ئ‚ك‚ؤپA‚‚çژq‚ة“n‚µ‚½پB
پ@ƒJƒٹƒLƒ…ƒ‰ƒ€‚ج•دچX‚ة”؛‚¢ƒTƒ|پ[ƒ^پ[چuچہ‚ًگVگف‚µ‚½‚ھپA‰•ه‚ھ‚ ‚邾‚낤‚©‚ئٹë‚ش‚ٌ‚إ
‚¢‚½2گl‚ج•sˆہ‚ح‰ًڈء‚µ‚½پB
پu‚±‚ٌ‚ب‚ة”½‹؟‚ھ‚ ‚é‚ئ‚حژv‚¢‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پv‚ئ‚ـ‚ë‚ف‚ح—x‚èڈo‚µ‚»‚¤‚إ‚ ‚éپBگV‚µ‚¢ƒJƒٹ
ƒLƒ…ƒ‰ƒ€‚إ‚حپAچuچہ‚ھ‚Q’iٹK‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB’mژ¯‚ئچl‚¦•û‚ً’†گS‚ئ‚µ‚½3ژٹش‚جپuٹî‘bچu
چہپvپB‚â‚è•û‚³‚¦•ھ‚©‚ê‚خپA‚ ‚ئ‚حژ©•ھ‚إ‚·‚¢‚·‚¢‚إ‚«‚éپIپ@‚ئ‚¢‚¤گl‚ح‚±‚±‚إ‘²‹ئپB
پ@گ®—‚ج‚â‚è•û‚ح‚ي‚©‚ء‚½‚¯‚اپA‚³‚ؤچs“®‚ةˆع‚·‚ج‚حچک‚ھڈd‚¢پA‰½‚©‚çژè‚ً‚آ‚¯‚ê‚خ‚¢‚¢‚ج
‚©پA‚ ‚ئˆê•à‚ھ“¥‚فڈo‚¹‚ب‚¢گl‚ج‚½‚ك‚ة‚ح1“ْ‚جƒڈپ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒvپB‚±‚±‚إ‚ح1گl‚ذ‚ئ‚è‚ھژہڈK
‚ً‚µ‚ب‚ھ‚çپA‚ب‚؛چs“®‚ةˆع‚¹‚ب‚¢‚ج‚©ژ©•ھ‚ةچ‡‚ء‚½•ذ•t‚¯•û‚ًچl‚¦‚ؤ‚à‚炤پB
پ@ƒTƒ|پ[ƒ^پ[چuچہ‚حپu‚ي‚‚ي‚•ذ•t‚¯چuچہپv‚جƒڈپ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒv‘²‹ئگ¶‘خڈغ‚إپA•ذ•t‚¯‚½‚¢‚¯
‚ا•ذ•t‚¯‚ç‚ê‚ب‚¢گl‚جƒTƒ|پ[ƒg‚ً‚·‚邽‚ك‚جچuچہ‚إ‚ ‚éپB
پ@ˆêŒû‚ة‚à‚ج‚ھ‘½‚¢‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚àپA•ّ‚¦‚ؤ‚¢‚éڈَ‹µ‚â–{گl‚جگ«ٹi‚ة‚و‚èˆل‚¤پBKژذ‚إ‚حƒTƒ|پ[ƒ^
پ[چuچہٹJچأ‚ة“–‚½‚èپA‚à‚ج‚ھ‘½‚¢ƒPپ[ƒX‚ً‘ه‚«‚‚R‚آ‚ة•ھ‚¯‚ؤ‚¢‚éپB
‚PپA‚à‚ج‚ھ‘½‚¢‚¯‚ê‚اپA“ْڈيگ¶ٹˆ‚إ‘ه‚«‚بژxڈل(‚à‚ج‚ھژU—گ‚µ‚ؤگQ‚éڈêڈٹ‚à‚ب‚¢‚ئ‚©)‚ھ‚ب‚¢
پ@پ@ڈêچ‡پB
‚QپA‘ج’²•s—ا‚â”F’mڈا‚ةگ¸گ_ژ¾ٹ³پA”ƒ•¨ˆث‘¶ڈا‚ب‚ا‚إپA‚©‚炾‚âگS‚جƒoƒ‰ƒ“ƒX‚ھ•ِ‚ê‚ؤ‚¢‚é
پ@پ@ڈêچ‡پB
‚RپA‰ئ‚â’ë‚ھ‚à‚ج‚إ‚ ‚س‚ê‚ؤ‚¢‚é‚à‚©‚©‚ي‚炸پA‘e‘ه‚²‚ف‚ًڈE‚ء‚ؤ—ˆ‚½‚èپA“ْڈيگ¶ٹˆ‚ةژxڈلپ@پ@
پ@پ@‚ھڈo‚ؤ‚¢‚é‚ة‚àٹض‚ي‚炸پA–{گl‚à‚µ‚‚ح‰ئ‘°‚ھ•ذ•t‚¯‚½‚¢‚ئژv‚ء‚ؤ‚¨‚ç‚·پA‚²‹كڈٹ‚©‚ç
پ@پ@‹êڈî‚جڈo‚ؤ‚¢‚郌ƒxƒ‹پBپi‚¢‚ي‚ن‚éƒSƒ~‰®•~پj
پ@ƒTƒ|پ[ƒ^پ[‚ح‚±‚ج’†‚إ‚P‚جگlپA‚©‚آ•ذ•t‚¯‚½‚¢‚ئ‚¢‚¤ˆسژv‚ج‚ ‚éگl‚ً‘خڈغ‚ة‚·‚éپB•ذ•t‚¯
‚½‚‚ب‚¢گl‚ة‘Pˆس‚ج‰ں‚µ”„‚è‚ح‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚à–Y‚ê‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢پB
پ@‚Q‚â‚R‚حˆم—أ‚جگê–ه‰ئ‚جƒTƒ|پ[ƒg‚ھ•K—v‚إپA‘fگl‚ھ‰؛ژè‚ةژè‚ًڈo‚·‚ئƒgƒ‰ƒuƒ‹‚ھ‹N‚±‚é‰آ
”\گ«‚ھ‚ ‚é‚ج‚إپAژ©•ھ‚ج—ح‚ً‰كگM‚µ‚ب‚¢‚و‚¤‚ة’چˆس‚ً‘£‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
پ@ƒTƒ|پ[ƒ^پ[‚ًƒڈپ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒv‘²‹ئگ¶‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپAژ©•ھ‚ھ•ّ‚¦‚ؤ‚¢‚½–â‘è‚ً‰ًŒˆ‚µ‚½گl
‚ة‚±‚»پA‚»‚جŒoŒ±‚ً“`‚¦‚ؤ—~‚µ‚¢‚ئژv‚¤‚©‚ç‚إ‚ ‚éپBژdژ–‚جڈê‚ئ‚µ‚ؤٹî–{‚حƒVƒ‹ƒoپ[گlچقƒZ
ƒ“ƒ^پ[‚ة“oک^‚µ‚ؤٹˆ“®‚·‚é‚ج‚إپAژû“ü‚ئ‚µ‚ؤ‚ح‘½‚‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًڈ³’m‚جڈم‚إ‚جƒTƒ|پ[ƒ^پ[ٹˆ“®
‚إ‚ ‚éپB
پ@ژv‚¢‚ھ‚¯‚ب‚¢”½‹؟‚إ‚ـ‚ë‚ف‚ج’e‚ٌ‚¾گ؛‚ةپA‚»‚¤‚ث‚ئƒnƒKƒL‚ج–¼‘O‚ئژَچu“®‹@‚ًŒ©‚ب‚ھ‚ç‚
‚çژq‚حپu‚ي‚‚ي‚•ذ•t‚¯چuچہپv‚ج‘²‹ئگ¶‚جٹç‚ًژv‚¢•‚‚©‚ׂ½پB
پ@ˆê”ش‘½‚©‚ء‚½‚ج‚حپA•s—v‚ب‚à‚ج‚ً•ذ•t‚¯‚ؤ‚ا‚ꂾ‚¯‚·‚ء‚«‚肵‚½‚©پA•é‚炵‚ھ•د‚ي‚ء‚½
‚©پAژ©•ھ‚جŒoŒ±‚ًگl‚ة“`‚¦‚½‚¢‚ئ‚¢‚¤‚à‚جپB‚ـ‚½‚±‚ê‚حƒSƒ~‰®•~‚ج–â‘è‚ئ‹¤‚ةپA‚¢‚¸‚êژذ‰ï
–â‘è‚ة‚ب‚é‚©‚çپAڈ‚µ‚إ‚àگ¢‚ج’†‚ةچvŒ£‚µ‚½‚¢‚ئ‚¢‚¤ژ‹“_‚à‚ ‚ê‚خپA’Pڈƒ‚ةپuƒTƒ|پ[ƒgپv‚ئ
‚¢‚¤—§ڈê‚ة–£—ح‚ًٹ´‚¶‚½گl‚à‚¢‚½پB
پ@‚‚çژq‚حˆب‘O‚©‚炱‚جٹé‰و‚ًچl‚¦‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‚ب‚©‚ب‚©ژہچs‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½پB
‚»‚±‚ضŒ»چف‚ح•ڈژqƒzپ[ƒ€‚ًŒo‰c‚µ‚ؤ‚¢‚邳‚‚çپi‡‚10پA•ڈژqƒzپ[ƒ€‚ً‚آ‚‚è‚ـ‚·پI“oڈêپj‚©
‚çƒپپ[ƒ‹‚إپu‚³‚ء‚³‚ئ‚â‚è‚ب‚³‚¢پv‚ئْ‚ھ”ٍ‚ٌ‚¾پB
پ@‚±‚¤‚µ‚ؤ‚³‚‚ç‚ةŒم‰ں‚µ‚³‚ê‚éŒ`‚إƒTƒ|پ[ƒ^پ[چuچہ‚ًٹJچu‚µ‚½پB
‚³‚‚çH‚پA2گl‚ھ‚¢‚‚çپu‚ي‚‚ي‚•ذ‚أ‚¯چuچہپv‚إٹو’£‚ء‚ؤ‚àپAچ»”™‚ة500ƒ~ƒٹ‚جƒyƒbƒgƒ{
ƒgƒ‹‚إگ…‚ً‚ـ‚‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚وپB‚»‚ê‚و‚è500ƒ~ƒٹ‚إ‚¢‚¢‚©‚çپA‚ـ‚گl‚ً‘‚₵‚ب‚³‚¢‚ئŒ¾‚ي
‚ꂽپBٹm‚©‚ة‚»‚¤‚¾پA‚‚çژq‚à“ھ‚إ‚ح‚ي‚©‚ء‚ؤ‚¢‚½‚à‚ج‚جچs“®‚ةˆع‚¹‚ب‚¢‚إ‚¢‚½پB
پ@2گl‚ھ‹ء‚¢‚½‚ج‚حپAچ،‰ٌ‚جچuچہ‚إ’jگ«‚ھ3•ھ‚ج1‚ًگè‚ك‚½‚±‚ئ‚¾‚ء‚½پB
چ،‚ـ‚إ‚جچuچہ‚إ‚±‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ح‚ب‚©‚ء‚½پBƒJƒٹƒLƒ…ƒ‰ƒ€‚ج•دچX‚إژ—چ‡‚¤گF‚جƒpپ[ƒ\ƒiƒ‹ƒJƒ‰پ[
‚âƒپƒCƒN‚ھƒIƒvƒVƒ‡ƒ“چuچہ‚ة‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚ئپAچإ‹ك–â‘è‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éƒSƒ~‰®•~‚âپAƒeƒŒƒr‚إژو
‚èڈم‚°‚ç‚ꂽ–³‰ڈژ€‚ج–â‘è‚ھ’j‚½‚؟‚جڈd‚¢چک‚ًڈم‚°‚³‚¹‚½‚炵‚¢پB
پ@ƒTƒ|پ[ƒ^پ[چuچہ‚إٹw‚رپA‚à‚ج‚ًŒ¸‚ç‚·‚±‚ئ‚âژ©‚ç‚ج‘جŒ±‚ً“`‚¦پAژذ‰ï‚ةچvŒ£‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚±
‚ئ‚à“®‹@‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB’è”N‚إژdژ–‚ً—£‚ꂽ’j‚½‚؟‚ھ“ث‘R’nˆو‚جƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒB‚ة
”ٍ‚رچ‚ٌ‚¾‚èپAƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA‚ً‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حƒnپ[ƒhƒ‹‚ھچ‚‚¢پB‚©‚ئ‚¢‚ء‚ؤچs‚ڈٹ‚à‚ب‚‰ئ
‚ة‚¢‚é‚ئ‚ت‚ê—ژ‚؟—t‚ئ‚¢‚ي‚êپAچب‚ئ‹¤‚ةڈo‚©‚¯‚و‚¤‚ئ‚·‚é‚ئ—F’B‚ئ—V‚ر‚ةچs‚‚©‚ç‚آ‚¢‚ؤ‚
‚é‚ب‚ئژ׌¯‚ة‚³‚ê‚éپB
‚µ‚©‚µ•ذ•t‚¯‚جƒTƒ|پ[ƒ^پ[‚ة‚ب‚ê‚خ‚â‚è‚ھ‚¢‚ھ‚ ‚èپAگ¶‚«‚ھ‚¢‚ة‚ب‚èپA‰ïژذ‚ئ‚¢‚¤‘gگD‚إŒ¨
ڈ‘‚ئ‹¤‚ة“‚¢‚ؤ‚«‚½’j‚½‚؟‚جژ©‘¸گS‚ً‚‚·‚®‚é‚ج‚¾‚낤پBƒTƒ|پ[ƒ^پ[‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚àپAژû“ü‚ح‚ي
‚¸‚©‚ب‚à‚ج‚¾‚ھپAگl‚ج–ً‚ة—§‚آ‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھƒGƒlƒ‹ƒMپ[‚ة‚ب‚é‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB
پ@’jگ«‚جƒTƒ|پ[ƒ^پ[‚ھ‘‚¦‚ؤپA’j‚½‚؟‚جƒlƒbƒgƒڈپ[ƒN‚ھچL‚ھ‚ê‚خƒSƒ~‰®•~‚ج—\–h‚ة‚à‚ب‚é‚©
‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB‚³‚‚ç‚ح‚±‚ج‚±‚ئ‚àŒ©’ت‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚¾‚낤‚©‚ئژv‚¢‚ب‚ھ‚ç‚‚çژq‚ح‚ع‚ٌ‚â‚è‘‹
‚ة–ع‚ً‚â‚ء‚½پB
پ@ƒٹƒTƒCƒNƒ‹ƒVƒ‡ƒbƒvپu‚ذ‚«‚ئ‚è‚âپv‚جŒ’‚³‚ٌ‚±‚ئڈ¬ں؛Œ«ژ،‚ھƒrƒ‹‚ج‘O‚ة‚¢‚éپB
پi‡‚‚UپA•ذ•t‚©‚ب‚¢‚©‚ç—£چ¥پ@“oڈêپj
‘‹‚ًٹJ‚¯‚ؤ‚‚çژq‚حپAŒ’‚³‚ٌ‚¤‚؟‚ة‚²—p‚إ‚·‚©‚ئگ؛‚ً‚©‚¯‚½پB
پ@ڈ¬ں؛‚حژè“yژY‚ج“¤‘ه•ں‚ً‚ـ‚ë‚ف‚ة“n‚µ‚½پB
پu‹ك‚‚ة—p‚ھ‚ ‚ء‚½‚à‚ج‚¾‚©‚çپcپv
پ@‚ ‚¢•د‚ي‚炸پAچ‚‘qŒ’‚ًگ’”q‚µ‚ؤ‚¢‚é’تڈجŒ’‚³‚ٌ‚حŒ¾—t‚àڈ‚ب‚¢پBچإ‹ك‚جƒٹƒTƒCƒNƒ‹ژ–ڈî
‚ً•·‚±‚¤‚ئژv‚ء‚½‚‚çژq‚ةپAڈ¬ں؛‚حژہ‚حچ¢‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚ئژٌ‚ةژè‚ً‚â‚ء‚½پB
پ@82چخ‚ج’jگ«‚ھپA3”N‘O‚ةژè•ْ‚µ‚½ژش’\گyپi‚‚é‚ـ‚¾‚ٌ‚·پj‚â’ƒ’I‚ً•ش‚¹‚ئ‚¢‚¤‚ج‚إ‚ ‚éپB
چœ“ں•i‚ئ‚µ‚ؤ‰؟’l‚ھ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤‚ظ‚ا‚ج‚à‚ج‚إ‚à‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إپA‚ي‚¸‚©‚ب’l’i‚µ‚©‚آ‚©‚ب‚©‚ء
‚½پB‚ق‚µ‚ëڈ¬ں؛‚حƒSƒ~‚إڈo‚¹‚خ‚¨‹à‚ًژو‚ç‚ê‚é‚ج‚¾‚©‚çپA‚ي‚¸‚©‚إ‚à‹à‚ھ“ü‚ê‚خ‰¶‚جژڑ‚إگl
ڈ•‚¯‚¾‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پu‚ا‚¤‚â‚çپAƒ{ƒP‚ھ‚ح‚¶‚ـ‚ء‚½‚ف‚½‚¢‚ب‚ٌ‚¾پB‚¤‚؟‚ھڈںژè‚ةژ‚ء‚ؤچs‚ء‚½‚ئ‹كڈٹ‚إگپ’®‚µ‚ؤ
‚é‚炵‚¢پv
پu‚à‚؟‚ë‚ٌپA‚»‚ج‚½‚ٌ‚·‚ح‚à‚¤‚ب‚¢‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پHپv
ڈ¬ں؛‚حèُ‚¢‚½پB
پu‚²‰ئ‘°‚حپHپv
پu”ھ‰¤ژq‚ة‘§ژq‚ھ‚¢‚é‚炵‚¢‚¯‚اپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚اٹٌ‚è‚آ‚©‚ب‚¢‚ف‚½‚¢‚إپA‚ذ‚ئ‚è•é‚炵پv
پu“‚¢ƒPپ[ƒX‚إ‚·‚ثپv
پ@ڈd‹ê‚µ‚¢‹َ‹C‚ً”j‚ء‚ؤپA‚ـ‚ë‚ف‚ھ‚¨’ƒ‚ً‰^‚ٌ‚إ‚«‚½پB
پu‚¨ژ‚½‚¹‚ج“¤‘ه•ں‚إپ[‚·پv
‚ـ‚ë‚ف‚àچہ‚ء‚ؤ“¤‘ه•ں‚ً–j’£‚è‚ب‚ھ‚çپA•·‚¢‚½پB
پu‚¨‚¶‚¢‚³‚ٌ‚ة‚¨—F’B‚ئ‚©پAگe‚µ‚¢گl‚ح‚¢‚ب‚¢‚ج‚إ‚·‚©پv
پu‚»‚ê‚ھ‚ث‚¦پAگج‚حژs‹c‰ï‚ج‹c’·‚¾‚ء‚½‚»‚¤‚إگl‚ة“ھ‚ً‰؛‚°‚½‚è‚إ‚«‚ب‚¢گl‚¾‚©‚çپcپv
ڈ¬ں؛‚ج“ڑ‚¦‚ة2گl‚ح”[“¾‚µ‚½پBژ©•ھ‚ج–ًگE‚âژdژ–‚ة‘خ‚µ‚ؤ‚جŒhˆس‚ًٹ¨ˆل‚¢‚µ‚ؤپAŒب‚ھˆج‚¢‚ئژv
‚¢چ‚ٌ‚إ‚µ‚ـ‚¤پB‚ـ‚½‚¹‚ء‚©‚‚جگl‚جŒْˆس‚ً‘f’¼‚ةژَ‚¯ژو‚ꂸپAŒا—§‚µ‚ؤˆسŒإ’n‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢
‚پB‚±‚جƒ^ƒCƒv‚ح’jگ«‚ة‘½‚ڈ¬ں؛‚جŒû‚ح‚ـ‚·‚ـ‚·ڈd‚‚ب‚ء‚½پB
پu‚ا‚¤‚â‚çپA‰حŒ´‚إƒ‚ƒm‚ًڈE‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤ‚é‚ف‚½‚¢‚ب‚ٌ‚¾پv
ƒLƒƒپ[پAƒSƒ~‰®•~پIپ@‚ئ‚ـ‚ë‚ف‚ھ‘f‚ء“ع‹¶‚بگ؛‚ً‚ ‚°‚½پB
‚±‚ꂱ‚ê‚ئپA‚‚çژq‚ح‚ـ‚ë‚ف‚ً‚½‚µ‚ب‚ك‚½پB
پu‚»‚ê‚إپA‰ئ‚ج’†‚ح‚ا‚¤‚ب‚ء‚ؤ‚é‚ج‚إ‚·‚©پv
پu’N‚à‰ئ‚ة“ü‚ê‚ب‚¢‚©‚çپA‚و‚‚ي‚©‚ç‚ب‚¢‚¯‚ê‚اپA‚½‚ش‚ٌپcپv
پu‚»‚ê‚إپA‚»‚ج‚¨‚¶‚¢‚³‚ٌ‚حپA’N‚ةŒ’‚³‚ٌ‚ھ’\گy‚ً“گ‚ء‚½‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚é‚ج‚إ‚·‚©پv
پu‹كڈٹ‚جŒً”ش‚ج‚¨‚ـ‚ي‚肳‚ٌپv
پuOh,پ@NoپIپv‚ئ‚ـ‚ë‚ف‚حŒ¨‚ً‚·‚‚ك‚½پB
پu‚»‚ê‚إپAŒ’‚³‚ٌ‚حŒxژ@‚©‚çژ–ڈî’®ژو‚إ‚·‚©پHپv
پu‚ـ‚ پAŒü‚±‚¤‚àڈ³’m‚µ‚ؤ‚é‚ف‚½‚¢‚إپAٹm”F‚ج“dکb‚إچد‚ٌ‚¾‚¯‚اپv
پ@ڈ¬ں؛‚جکb‚ة‚و‚é‚ئپAچ،‚ـ‚إ‚ة‚à“X‚ة•i•¨‚ًژ‚ء‚ؤ—ˆ‚½ژ‚ح‚¢‚‚ç‚إ‚àˆّ‚«ژو‚ء‚ؤ‚à‚炦‚ê
‚خ‚ ‚è‚ھ‚½‚¢‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚½‚‚¹‚ةپAŒم‚©‚ç‚ ‚ê‚ح‚à‚ء‚ئ‰؟’l‚ ‚é•i‚¾‚ء‚½‚©‚ç•ش‚µ‚ؤ‚‚ê‚ئŒ¾
‚¤گl‚ح‚¢‚½پB‚µ‚©‚µچ،‰ٌ‚حکb‚ھˆل‚¤پB
‚»‚ê‚ةڈ¬ں؛‚حپu‚ذ‚«‚ئ‚è‚âپv‚ھ’†ڈ‚³‚ê‚邱‚ئ‚و‚èپA‚»‚جکV–ê‚ج‚±‚ئ‚ًˆؤ‚¶‚ؤ‚¢‚éپB‚©‚ئ‚¢
‚ء‚ؤ—]Œv‚ب‚¨‚¹‚ء‚©‚¢‚ح‚µ‚½‚‚ب‚¢پB
‚‚çژq‚ح‘أ“–‚بگü‚ً’ٌˆؤ‚µ‚½پB
پu’¬“à‰ï‚ج‰ï’·‚³‚ٌ‚ئ‚©پA–¯گ¶ˆدˆُ‚ج•û‚ئ‚©‚»‚¤‚¢‚¤•û‚©‚炲‰ئ‘°‚ةکA—چ‚µ‚ؤ‚à‚炤‚ئ‚©پv
ڈ¬ں؛‚ھ‚»‚جژè‚ح‚à‚¤ژژ‚µ‚½‚ئژٌ‚ًگU‚ء‚½پB
‚‚çژq‚ح‚±‚ê‚àƒ_ƒپ‚©‚ئ‚ذ‚ئ‚育‚؟‚½پB
پu‚‚çژq‚³‚ٌ“‚¢ٹç‚ً‚µ‚ؤ‚ب‚¢‚إپAŒ’‚³‚ٌ‚ج“¤‘ه•ں‚ً‚¢‚½‚¾‚¢‚½‚ç‚ا‚¤‚إ‚·‚©پv
‚ـ‚ë‚ف‚ح2‚آ–ع‚ة‚©‚ش‚è‚آ‚¢‚ؤ‚¢‚éپB
‚»‚¤‚ث‚¦‚ئ‹êڈخ‚µ‚ب‚ھ‚çپA‚‚çژq‚ح‰ظژq”«‚ج“¤‘ه•ں‚ًژè‚ة‚µ‚½پB
پ@ڈ¬ں؛‚ح‚ھ‚ش‚è‚ئ’ƒ‚ًˆù‚ٌ‚¾پB‚‚çژq‚جٹç‚ھ“ث‘R‹P‚¢‚½پB
پuٹm‚©پAگ¸گ_‰بˆم‚إƒSƒ~‰®•~‚جƒTƒ|پ[ƒg‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚éگوگ¶‚ھ‚¨‚ç‚ꂽ‚ح‚¸پv
ڈ¬ں؛‚ح–{“–‚©‚ئ‚¢‚¤ٹç‚إ‚‚çژq‚ًŒ©‚½پB
پ@ژ‘—؟‚ًژè‚ةپA‚‚çژq‚ھ‰گعƒRپ[ƒiپ[‚ة–ك‚é‚ئڈ¬ں؛‚ھ“¤‘ه•ں‚ًگH‚ׂؤ‚¢‚½پB
پu‚ـ‚ پAŒ’‚³‚ٌ‚حٹأ‚¢‚à‚ج‚ھŒ™‚¢‚¶‚ل‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚©پv
‹ء‚‚‚çژq‚ةپAŒ’‚³‚ٌ‚à“¤‘ه•ں‚جˆذ—ح‚ة‹C‚ھ‚آ‚¢‚½‚»‚¤‚إ‚·‚ئپA‚ـ‚ë‚ف‚ھ‚¤‚ꂵ‚»‚¤‚ة3‚آ–ع
‚ة‚©‚ش‚è‚آ‚¢‚½پBپ@
پ@ڈ¬ں؛‚ھ‚‚çژq‚ھڈذ‰î‚µ‚½گ¸گ_‰بˆم‚ة‘ٹ’k‚µ‚ؤ‚ف‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إپAکb‚حڈI‚ي‚ء‚½پB
پuŒ’‚³‚ٌ‚à‚¢‚¢گl‚إ‚·‚ث‚¦پA‚ ‚©‚ج‘¼گl‚ج‚¨‚¶‚¢‚³‚ٌ‚جژ–‚إ‚»‚±‚ـ‚إ‚·‚é‚ب‚ٌ‚ؤپv
پu‚»‚ج•û‚ھ–S‚‚ب‚ء‚½‚¨•ƒ‚³‚ٌ‚ةژ—‚ؤ‚ç‚ء‚µ‚ل‚é‚炵‚¢‚ج‚وپv
پuٹç‚ھپHپ@ژ—‚ؤ‚é‚ٌ‚إ‚·‚©پv
پuٹç‚ئ‚©‚¶‚ل‚ب‚‚ؤپA–¾ژ،‚ج’j‚ئŒ¾‚¤‚©پAٹوŒإ‚إگl‚ً—ٹ‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢گl‚¾‚ء‚½‚炵‚¢
‚يپv
‚بپ[‚é‚ظ‚اپAŒ’‚³‚ٌ‚炵‚¢‚ئ”[“¾‚µ‚ؤ‚ـ‚ë‚ف‚حژdژ–‚ج‘±‚«‚ً‚·‚邽‚ك‚ةƒpƒ\ƒRƒ“‚ةŒü‚©‚ء
‚½پB
پ@‚‚çژq‚ح‰ü‚ك‚ؤپAƒTƒ|پ[ƒ^پ[چuچہ‚جڈd—vگ«‚ًچl‚¦‚½پB
ˆب‘OپuƒCƒ“ƒ^پ[ƒlƒbƒg’ƒ‰®پv‚جŒن“°•vچب‚ة’jگ«Œü‚¯‚ج•ذ•t‚¯چuچہ‚جٹé‰و‚ًˆث—ٹ‚³‚ꂽ‚ھپA‚ـ
‚¾ژہچs‚إ‚«‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB
پi‡‚19پAƒSƒ~‰®•~‚ج’j‚â‚à‚كƒvƒچƒWƒFƒNƒgپ@“oڈêپj
پ@‚µ‚©‚µٹî‘bچuچہ‚جƒJƒٹƒLƒ…ƒ‰ƒ€‚ً•دچX‚µ‚½‚±‚ئ‚إپAڈ—گ«‚¾‚¯‚إ‚ب‚’jگ«‚àژَچu‚µ‚ؤ‚à‚炦
‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پB
پ@ƒTƒ|پ[ƒ^پ[چuچہ‚ً‘²‹ئ‚µ‚½گl‚½‚؟‚ة‚حپA‚؛‚ذ“¯‚¶‚و‚¤‚ب”Y‚ف‚ً•ّ‚¦‚ؤ‚¢‚éگl‚½‚؟‚ة‘جŒ±‚ً
•ھ‚©‚؟چ‡‚¤‚±‚ئ‚إپA—ض‚ًچL‚°‚ؤ—~‚µ‚¢‚ئژv‚ء‚½پB
پ@چuچہ‚جڈ‰“ْ‚حڈHگ°‚ê‚ج—ا‚¢“V‹C‚إپAچKگو‚ج‚و‚¢ƒXƒ^پ[ƒg‚¾‚ئژv‚ي‚ꂽپB
پ@ƒTƒ|پ[ƒ^پ[چuچہ‚حŒv18ژٹش‚إ3“ْ‚ة‹y‚شپB‚‚çژq‚حƒڈپ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒv‚ج‘²‹ئگ¶‚ھ‚ا‚ê‚‚ç‚¢
ژQ‰ء‚µ‚ؤ‚‚ê‚é‚©گS”z‚¾‚ء‚½‚ھ—\‘z‚ًڈم‰ٌ‚éگ”‚¾‚ء‚½پB
‚ب‚؛گS”z‚¾‚ء‚½‚©‚ئ‚¢‚¦‚خپA‚½‚¾ƒڈپ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒv‚ًڈC—¹‚µ‚½‚ج‚إ‚حƒTƒ|پ[ƒ^پ[چuچہ‚جژَچu‚ح
‚إ‚«‚ب‚¢‚©‚炾پBژ©•ھژ©گg‚ھ•é‚炵‚âگ¶‚«•û‚ًچl‚¦پA•ذ•t‚¯‚ًچد‚ـ‚¹‚ب‚¢‚ئƒTƒ|پ[ƒ^پ[‚ئ‚µ
‚ؤژ©گM‚ًژ‚ء‚ؤژَچuژز‚ة‘جŒ±‚ًکb‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢‚©‚ç‚إ‚ ‚éپB
پ@‚±‚جچuچہ‚إ‚حٹî‘bچuچہ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح‚à‚؟‚ë‚ٌ‚¾‚ھپAƒTƒ|پ[ƒ^پ[‚ئ‚µ‚ؤ‚جٹî‘b“I‚ب’mژ¯پAƒ}ƒi
پ[پA‚»‚ج‘¼ژہ–±“I‚ب‚±‚ئ‚àٹـ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚éپBڈم‚©‚ç–عگü‚إ‚ب‚پA•ذ•t‚¯‚ًŒoŒ±‚µ‚½ژ¸”s’k‚ئ‹¤
‚ةگو”y‚ئ‚µ‚ؤ‚ج—§ڈê‚إŒê‚ء‚ؤ‚à‚炤ƒXƒ^ƒCƒ‹‚إ‚ ‚éپB
پ@ٹ÷ڈم‚ج‹َک_پHپIپ@‚و‚è‚ذ‚ئ‚آ‚ج‘جŒ±پIپ@‚»‚ê‚ھ‚ث‚ç‚¢‚إ‚ ‚éپB
‚ـ‚½ƒTƒ|پ[ƒ^پ[‚ھ‚¢‚«‚¢‚«‚ئٹˆ–ô‚·‚éژp‚ھ‚ذ‚ئ‚آ‚جƒ‚ƒfƒ‹‚ة‚ب‚ê‚خپAŒم‚ة‘±‚گl‚à‘‚¦‚邾
‚낤پB‚±‚ج‚و‚¤‚بˆس–،‚إ‚à‘و1‰ٌ‚جƒTƒ|پ[ƒ^پ[چuچہ‚حڈd—v‚إ‚ ‚éپB‚‚çژq‚حگg‚ج‚ذ‚«‚µ‚ـ‚éژv
‚¢‚¾‚ء‚½پB
پ@’èˆُ15–¼‚ة16–¼‚ج‰•ه‚إپA1–¼‚‚ç‚¢‚ح“–“ْ‚جƒLƒƒƒ“ƒZƒ‹‚ھ‚ ‚é‚©‚ئژv‚¢16–¼‚ةژَچu•[‚ً
‘—‚ء‚½‚ھپA‘Sˆُڈoگب‚¾‚ء‚½پB‚±‚جگ¢‘م‚جگlپX‚ح‚¨‚¨‚ق‚ث‚ـ‚¶‚ك‚إ‚ ‚éپB‚ـ‚½گ\‚µچ‚ف‚àپA‚ح
‚ھ‚«‚©ƒtƒ@ƒbƒNƒX‚ب‚ج‚إ‚ظ‚ئ‚ٌ‚اژèڈ‘‚«‚إ‚ ‚éپB
پ@ژ©•ھ‚إژèٹش‰ة‚©‚¯‚ؤگ\‚µچ‚ق‚ج‚ئپAƒCƒ“ƒ^پ[ƒlƒbƒg‚âƒXƒ}ƒz‚إگ\‚µچ‚ق‚ج‚ئ‚إ‚ح–¾‚ç‚©‚ة
ˆل‚¢‚ھ‚ ‚éپBچ،‚إ‚حƒlƒbƒg‚إگ\‚µچ‚ف‚جچuچہ‚ھ’f‘R‘½‚¢پB‚µ‚©‚µƒlƒbƒg‚إٹب’P‚ةگ\‚µچ‚قگl
‚حکA—چ‚à‚¹‚¸‚ة‹x‚ٌ‚¾‚èپA‚ذ‚ا‚¢‚ج‚حگ\‚µچ‚ٌ‚¾‚±‚ئ‚³‚¦–Y‚ê‚ؤ‚¢‚½‚è‚·‚éپB
پ@ƒJƒ‹ƒ`ƒƒپ[ƒZƒ“ƒ^پ[‚ج’mگl‚ة•·‚¢‚½کb‚إ‚حپA‚ ‚éچuچہ‚إ30–¼‚ج•هڈW‚ة45–¼‚جگ\‚µچ‚ف‚ھ‚
‚èپA40–¼‚ةژَچu’ت’m‚ًڈo‚µپA5–¼‚حƒLƒƒƒ“ƒZƒ‹‘ز‚؟‚¾‚ء‚½پB‚»‚ê‚ة‚àٹض‚ي‚炸ڈoگب‚ح22–¼‚إ
Œ‡گب‚جکA—چ‚à“–“ْ’©‚ج1–¼‚¾‚¯پB‚±‚ê‚إ‚حƒLƒƒƒ“ƒZƒ‹‘ز‚؟‚جگl‚ةکA—چ‚à‚إ‚«‚ب‚¢پB‹ك‚²‚ë‚إ‚ح
ˆùگH“X‚ج—\–ٌ‚à–â‘è‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‚±‚¤‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھŒ»ژہ‚ة‹N‚±‚ء‚ؤ‚¢‚éژ‘م‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپB
پ@چ،‰ٌ‚جژَچuژز‚ح5–¼‚ھ’jگ«پB‚‚çژq‚ھ‚ب‚é‚ظ‚ا‚ئژv‚ء‚½‚ج‚حپA5–¼‚ج‚¤‚؟4–¼‚ھƒlƒNƒ^ƒC‚ً
’÷‚كپAژc‚è1–¼‚حƒmپ[ƒlƒNƒ^ƒC‚¾‚ھپAƒWƒƒƒPƒbƒg‚ةƒڈƒCƒVƒƒƒc‚إ‚ ‚éپB‚آ‚ـ‚è‘Sˆُژdژ–ƒ‚پ[ƒh
‚إژذˆُŒ¤ڈC‚ئ‚¢‚¤ٹ´‚¶‚¾‚낤‚©پBڈ—گ«‚ح‚ئŒ¾‚¦‚خ‚±‚ê‚ح—lپX‚إپAƒXپ[ƒcژp‚ح2گlپAƒZپ[ƒ^پ[‚ھ
5گlپAƒJپ[ƒfƒBƒKƒ“‚ھ2گlپAƒgƒbƒNƒٹ‚جƒZپ[ƒ^پ[‚ةƒxƒXƒg‚ھ2گl‚¾‚ء‚½پB
پ@ƒTƒ|پ[ƒ^پ[چuچہ‚حژ©Œبڈذ‰î‚©‚çژn‚ـ‚éپB‚‚çژq‚ح1گl‚¸‚آƒzƒڈƒCƒgƒ{پ[ƒh‚ج‘O‚إژ©Œبڈذ‰î‚ً
‚µ‚ؤ‚à‚炤‚±‚ئ‚ة‚µ‚½پBژ‚؟ژٹش‚ح1گl3•ھپB3•ھ‚ئ‚¢‚¦‚خ’Z‚¢‹C‚à‚·‚é‚ھپA‚«‚؟‚ٌ‚ئ‚µ‚ل‚×
‚낤‚ئژv‚¤‚ئŒ‹چ\’·‚¢پB
پ@ژ©Œبڈذ‰îˆê”شژè‚ج‘هژR‹`–¾‚حپA’©—ç‚إکb‚·‚و‚¤‚ةٹµ‚ꂽŒû’²‚إŒo—ً‚ًŒê‚ء‚½پB3”N‘O‚ـ‚إ‹خ
‚ك‚ؤ‚¢‚½‰ïژذ‚حژذˆُ300گl‚جچHچى‹@ٹB‚جچHڈê‚إپA‘هژR‚حچHڈê’·‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½پBچHڈê‚إ‚ح“–‘RپA
چH‹ï‚ج”z’u‚âگ®—گ®“ع‚ح—¦گو‚µ‚ؤچs‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ھپAژ©‘î‚ج•ذ•t‚¯‚ئ‚ب‚é‚ئ‚¨ژèڈم‚°‚¾‚ء‚½پB
پ@’è”NŒمپAˆêگl•é‚炵‚ة‚ب‚ء‚ؤ“r•û‚ة•é‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚±‚ë‚ةپu‚ي‚‚ي‚•ذ‚أ‚¯چuچہپv‚ج‚±‚ئ‚ً
’m‚ء‚½پBگ¢ٹش‚جŒi‹C‚ح—ا‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚炵‚¢‚ھ‘هژR‚حچؤڈAگE‚ج‚ ‚ؤ‚à‚ب‚پAژٹش‚¾‚¯‚ح‚ ‚é
‚ج‚إ—â‚â‚©‚µ”¼•ھ‚إژQ‰ء‚µ‚½پBچHڈê‚ئ“¯‚¶‚و‚¤‚ة•K—v‚ب‚à‚ج‚ً•K—v‚ب‚ئ‚±‚ë‚ة’u‚«پAژû”[‚·
‚é‚à‚ج‚حژو‚èڈo‚µ‚â‚·‚¢‚ئ‚±‚ë‚ة“ü‚êپA•s—p‚ب‚à‚ج‚حڈˆ•ھ‚·‚éپAٹî–{‚ح“¯‚¶‚¾‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ
‚ي‚©‚ء‚½پB
پ@چHڈê‚ج‚à‚ج‚ج”z’u‚ًگà–¾‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚±‚ë‚إپA‚‚çژq‚ھƒ`ƒٹƒ“‚ئƒxƒ‹‚ً–آ‚炵پA3•ھ‚إ‚·‚ئگ؛
‚ً‚©‚¯‚½پB
پu‚±‚ê‚©‚ç‚ھ‚¢‚¢‚ئ‚±‚ë‚ب‚ج‚إ‚·‚ھپv‚ئ‘هژR‚حژc”O‚»‚¤‚¾پB
پu‚»‚ج‚¢‚¢‚ئ‚±‚ë‚ًکb‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚‚ج‚ھژ©Œبڈذ‰î‚إ‚ح‘هگط‚ب‚±‚ئ‚إ‚·‚ثپBٹF‚³‚ٌ‚ح‘هژR‚³‚ٌ
‚ج‚¨کb‚ج‘±‚«‚ً•·‚«‚½‚¢‚إ‚·‚©پv
ƒnƒC‚ئ“ڑ‚¦‚½‚èپA‚¤‚ب‚¸‚¢‚½‚è‚إٹF‚ھ‘±‚«‚ً‘ز‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھ‚¤‚©‚ھ‚ي‚ꂽپB
پ@ژہ‚ح‚ئ”–‚¢Œم“ھ•”‚ةژè‚ً‚ ‚ؤپA‘هژR‚ح“Vˆن‚ًŒ©ڈم‚°پAگO‚ً‚©‚ف‚µ‚ك‚½پB
پu’è”N‚µ‚½“r’[‚ةپAچب‚ھ—£چ¥‚µ‚½‚¢‚ئŒ¾‚¢ڈo‚µ‚ـ‚µ‚ؤپA‚¢‚₨’p‚¸‚©‚µ‚¢پB‚¢‚ي‚ن‚éڈn”N—£
چ¥‚ئ‚¢‚¢‚ـ‚·‚©پAچب‚âژq‚ا‚à‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚ي‚½‚µ‚حATM‚¾‚ء‚½‚»‚¤‚إپA’è”N‚ئ‹¤‚ة—p‚ب‚µ‚¾‚»‚¤
‚إپv
پ@Œû‚²‚à‚ء‚½‘هژR‚ةپA1”ش‘O‚جگب‚جŒُ“cٹ°ˆê‚ھ‹C‚ة‚·‚邱‚ئ‚ح‚ب‚¢‚إ‚·‚و‚ئگ؛‚ً‚©‚¯‚½پB
پ@‘هژR‚ح‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚·‚ئŒُ“c‚ةŒy‚“ھ‚ً‰؛‚°پAƒ|ƒPƒbƒg‚©‚ç‚‚µ‚ل‚‚µ‚ل‚جƒnƒ“ƒJ
ƒ`‚ًژو‚èڈo‚µ‚ؤٹz‚جٹ¾‚ًگ@‚¢‚½پB
پuATM‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚àپA‚ي‚½‚µ‚ة‚ح‚ا‚¤‚µ‚ؤ—£چ¥‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢‚ج‚©‚³‚ء‚د‚è‚ي‚©‚ç‚ب‚©
‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚ھپAچب‚ح‚»‚ج‚ي‚©‚ç‚ب‚¢‚ئ‚±‚ë‚ھ–â‘è‚ب‚ج‚¾‚ئپA—£چ¥“ح‚ً’u‚¢‚ؤ‚³‚ء‚³‚ئڈo‚ؤ‚¢
‚«‚ـ‚µ‚½پv
پ@‰ïڈê‚ة‚ح‹C‚ـ‚¸‚¢•µˆح‹C‚ھ—¬‚ꂽپB
پuچإڈ‰‚ح“ھ‚ة‚«‚ؤژً‚ًˆù‚ٌ‚¾‚肵‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚µ‚ه‚¹‚ٌ•v•w‚ح‘¼گl‚ب‚ج‚¾‚µپA‚¨Œف‚¢‚ة—‰ً‚إ
‚«‚ب‚¢‚ج‚ب‚ç•ت‚ꂽ•û‚ھ—ا‚©‚ء‚½‚ٌ‚¾‚ئژv‚¤‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB–¢—û‚ھ‚ب‚¢‚ئŒ¾‚¦‚خ‰R‚ة‚ب
‚è‚ـ‚·‚ھپcپv
پ@‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ـ‚إŒ¾‚ي‚ب‚‚ؤ‚¢‚¢‚ج‚ة‚ئ‚¢‚¤‹َ‹C‚ً‚و‚»‚ةپA‘هژR‚ح‘±‚¯‚½پB
پu’‹ٹش‚©‚çژً‚ًˆù‚ٌ‚إپA‰ئ‚ج’†‚à‚®‚؟‚ل‚®‚؟‚ل‚إƒJƒr‚ھگ¶‚¦‚»‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤپB‚ب‚ٌ‚ئ‚©‚µ‚ب‚¯
‚ê‚خ‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚éژ‚ةپAٹî‘bچuچہ‚جƒ`ƒ‰ƒV‚ھ—X•ضژَ‚¯‚ة“ü‚ء‚ؤ‚¢‚½‚à‚ج‚إپcپv
پ@‚‚çژq‚ئ‚ـ‚ë‚ف‚حٹç‚ًŒ©چ‡‚ي‚¹‚½پA‚»‚ê‚ح‚¨‚©‚µ‚¢پB
ƒ`ƒ‰ƒV‚جƒ|ƒXƒeƒBƒ“ƒO‚ً‹ئژز‚ةˆث—ٹ‚µ‚½‚±‚ئ‚ح‚ب‚¢‚µپAگV•·‚ةگـ‚èچ‚فچLچگ‚ً“ü‚ꂽ‚±‚ئ‚à
‚ب‚¢پB‚¾‚©‚ç—X•ضژَ‚¯‚ةƒ`ƒ‰ƒV‚ھڈںژè‚ة“ü‚é‚ح‚¸‚ھ‚ب‚¢‚ج‚إ‚ ‚éپB
پ@‘هژR‚ج”M•ظ‚ح‘±‚¢‚ؤ‚¢‚éپBٹî‘bچuچہ‚إƒJƒr‚ھگ¶‚¦‚»‚¤‚ب‰ئ‚ج’†‚ح‚ ‚é’ِ“x‚ـ‚إ•ذ•t‚¢‚½‚ھ
‚·‚ء‚«‚è‚ئ‚ـ‚إ‚ح‚¢‚©‚ب‚©‚ء‚½پB‚ـ‚½ٹî‘bچuچہ‚إ’m‚èچ‡‚ء‚½گl‚½‚؟‚ئ‚ج‰ïکb‚àٹy‚µ‚پAƒڈپ[
ƒNƒVƒ‡ƒbƒv‚àژَ‚¯‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پBگ³’¼‚ب‚ئ‚±‚ëپA‘¼‚ة‚±‚ê‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚·‚邱‚ئ‚à‚ب‚¢‚µƒTƒ|پ[
ƒ^پ[‚ة‚ب‚é‚ج‚àˆ«‚‚ح‚ب‚¢‚ب‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚½‚©‚ç‚إ‚ ‚éپB
پuڈ—–[‚ھپA‚¢‚âپAŒ³چب‚ھ‚¢‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ—ا‚©‚ء‚½‚ب‚ئژv‚¤‚±‚ئ‚حپA‰ئ‚ج’†‚إƒ^ƒoƒR‚ھ‹z‚¦‚é‚و
‚¤‚ة‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚إ‚·پB‘O‚حژَ“®‹i‰Œ‚¾‚ئ‚©پA‚½‚خ‚±‚ج‚ة‚¨‚¢‚ھƒJپ[ƒeƒ“‚ةˆع‚é‚ئ‚©پAٹD‚ھ”ٍ
‚ش‚ئ‚©پA‚¢‚ë‚¢‚낤‚邳‚Œ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚µ‚½‚ھچ،‚ح‚ج‚ر‚ج‚ر‚إ‚·پv
پ@‘هژR‚جŒ¾—t‚ح‚©‚猳‹C‚ة•·‚±‚¦‚é‚ھپA–{گl‚ح‹C•t‚¢‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB
‚‚çژq‚ھƒ`ƒٹƒٹƒ“‚ئƒxƒ‹‚ً–آ‚炵‚½پB
‚¦‚ءپA‚ـ‚¾پAڈI‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚إ‚·‚ھ‚ئپA‘هژR‚ح‚‚çژq‚ًŒ©‚½پB
پuژں‚ج•û‚àپA‘ز‚ء‚ؤ‚¨‚ç‚ê‚ـ‚·‚وپv
‘هژR‚ح‚µ‚ش‚µ‚شگب‚ة–ك‚ء‚½پB
پ@2”ش–ع‚ج‹ّ–{‚ ‚¸‚³‚حŒ³ƒAƒiƒEƒ“ƒTپ[‚إپAƒVƒƒƒlƒ‹ƒ^ƒCƒv‚ج”–‚¢ƒuƒ‹پ[‚جƒXپ[ƒc‚ً’…‚ؤپA—ژ
‚؟’…‚¢‚½گ؛‚إکb‚µ‚¾‚µ‚½پBƒ}ƒCƒN‚ًژg‚ي‚ب‚‚ؤ‚àپAگ؛‚ھ’ت‚èپA•·‚«‚â‚·‚¢پB
پ@‚â‚ء‚د‚è• ژ®Œؤ‹z‚إ‚µ‚ه‚¤‚©‚ث‚¦‚ئپA‚ـ‚ë‚ف‚ح‚¤‚ء‚ئ‚肵‚ؤ•·‚¢‚ؤ‚¢‚éپB
پu‚±‚±10”N‚ظ‚اکN“ا‚جƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA‚ً‚µ‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB2گl‚ج‘§ژq‚à‚و‚¤‚â‚“ئ—§‚µ‚ؤ‰ئ‚ج’†
‚ً•ذ•t‚¯‚و‚¤‚ئژv‚ء‚½ژ‚ةپw‚ي‚‚ي‚•ذ‚أ‚¯چuچہپx‚ج‚±‚ئ‚ً—Fگl‚©‚ç•·‚«پAژQ‰ء‚µ‚ـ‚µ‚½پB
‰ئ‚ھ‚·‚ء‚«‚肵‚½‚ج‚إ‚¨—F’B‚ً‚¨Œؤ‚ر‚µ‚½‚çپA•ذ•t‚¯•û‚ً‹³‚¦‚ؤ—~‚µ‚¢‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‹ء‚«‚ـ‚µ
‚½پB‚±‚؟‚ç‚جٹî‘bچuچہ‚ةژQ‰ء‚·‚é‚و‚¤‚ة‚¨ٹ©‚ك‚µ‚½‚ج‚إ‚·‚ھپA’m‚ç‚ب‚¢•û‚ئˆêڈڈ‚إ‚ح‹C‚ھگi
‚ـ‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إپA‚»‚ê‚ب‚ç‚ي‚½‚µ‚ھƒTƒ|پ[ƒ^پ[‚ة‚ب‚ء‚ؤژè“`‚¨‚¤‚©‚ئژv‚¢پAژQ‰ء‚µ‚ـ‚µ
‚½پv
پu‚ ‚¸‚³ƒ}ƒWƒbƒNپv‚ة‚©‚©‚ء‚½‚و‚¤‚ةپAٹF‚¤‚ب‚¸‚¢‚ؤ‚¢‚éپB
پ@‚‚çژq‚حپAکbڈp‚جچI‚ف‚³‚à‚ ‚é‚ھ‘ه•”•ھ‚ح‚ ‚¸‚³‚جگl•؟‚¾‚ئژv‚ء‚½پB
Œ³ƒAƒiƒEƒ“ƒTپ[‚إ‚ب‚‚ؤ‚àکb‚µ•û‚ج‚¤‚ـ‚¢گlپAگ؛‚ج‚و‚¢گl‚ح‚¢‚é‚ھپA‚»‚ꂾ‚¯‚إ‚حگl‚ح“®‚©
‚³‚ê‚ب‚¢پB•sژv‹c‚ب‚à‚ج‚إ‚¢‚‚ç•\–ت‚ًژو‚è‘U‚ء‚ؤ‚àپAگl‘O‚إکb‚ً‚·‚ê‚خگlٹشگ«‚ھ“§‚¯‚ؤŒ©
‚¦‚éپB
پu‚إ‚«‚ê‚خپAƒTƒچƒ“‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚ة‚µ‚½‚¢‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB•ذ•t‚¯‚جƒTƒ|پ[ƒg‚ئ‹¤‚ة—؟—‚â
‚¨‰ظژqپAƒlƒCƒ‹‚ج‹³ژ؛‚ً—\’肵‚ؤ‚¢‚ـ‚·پv
پ@ڈ—گ«‚ج‰½گl‚©‚جژَچuژز‚حپAژ©•ھ‚ة‚àƒTƒچƒ“‚ھڈo—ˆ‚é‚©‚µ‚ç‚ئ‹¹ژZ—p‚ًژn‚ك‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚ ‚¸‚³‚ھژٹش’ت‚è‚ةژ©Œبڈذ‰î‚ًڈI‚¦‚é‚ئپA”~گXگ´ژںکY‚ج”ش‚ة‚ب‚ء‚½پB
پ@”~گX‚حپA‚¦‚¦پ[‚ء‚ئپA‚ئŒ¾‚ء‚½‚«‚肵‚½‰؛‚ًŒü‚¢‚ؤŒ¾—t‚ھڈo‚ب‚¢پB‚ـ‚ë‚ف‚ھڈ•‚ءگl‚ةڈo‚ـ
‚µ‚ه‚¤‚©‚ئ‚‚çژq‚ة‚³‚³‚â‚¢‚½پB‚ـ‚ë‚ف‚ًگ§‚µ‚ؤپA‚‚çژq‚ھ”~گX‚ج‰،‚ة—§‚ء‚½پB
پu”~گX‚³‚ٌ‚ج‚¨‘î‚ح•ذ•t‚«‚ـ‚µ‚½‚©پv
ƒnƒC‚ئ‰‚¦‚ؤپA”~گX‚ح‚غ‚آ‚è‚غ‚آ‚è‚ئ•êگe‚ئ‚جگ¶ٹˆ‚ًŒê‚èژn‚ك‚½پB
پu•ê‚ئ“ٌگl•é‚炵‚إ‚·پB•ê‚ح‘«‚ھˆ«‚‚ؤپc‚¤‚؟‚ح•ƒ‚جˆâ•i‚à‚»‚ج‚ـ‚ـ‚¾‚µپA‚à‚ج‚ھ‚¢‚ء‚د‚¢
‚إ‚ا‚¤‚·‚ê‚خ‚¢‚¢‚©‚ي‚©‚ç‚ب‚‚ؤپcگV•·‚ئˆêڈڈ‚ةچuچہ‚جƒ`ƒ‰ƒV‚ھ“ü‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپB•ê‚ھ‚±‚±
‚ةچs‚ء‚ؤپA•ذ•t‚¯•û‚ًڈK‚ء‚ؤ‰ئ‚ً•ذ•t‚¯‚ؤ‚‚êپB‚»‚¤‚إ‚ب‚¢‚ئژ€‚ت‚ة‚àژ€‚ةگط‚ê‚ب‚¢‚ئŒ¾‚¤
‚à‚ج‚إپcپv
پ@گV•·‚ةƒ`ƒ‰ƒVپHپ@‚‚çژq‚ح‹ء‚«‚ً‰B‚µ‚ؤپAژd•û‚ب‚—ˆ‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½‚©‚ئ•·‚¢‚½پB
پ@”~گX‚حŒy‚ژٌ‚ًگU‚ء‚½پB
پu‚»پA‚»‚¤‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚إ‚·‚ھپA‚ا‚¤‚¢‚¤چuچہ‚©‚و‚‚ي‚©‚ç‚ب‚©‚ء‚½‚µپA‚»‚ê‚ةپc‚¦‚¦‚ئپv
”~گX‚جٹç‚ھ‚ف‚é‚ف‚éگش‚‚ب‚ء‚½پB
پuڈ—گ«Œü‚¯‚جچuچہ‚¾‚ئژv‚ي‚ꂽ‚ج‚إ‚حپHپv
”~گX‚ح‚ظ‚ء‚ئ‚µ‚½‚و‚¤‚ةپA‚±‚‚è‚ئ‚¤‚ب‚¸‚¢‚½پB
پu‚»‚ê‚إپA‚¨‘î‚ح•ذ•t‚«‚ـ‚µ‚½‚©پv
پu‚·‚ء‚«‚肵‚ؤپA•ê‚ھ‹Cژ‚؟—ا‚‚ب‚ء‚½پB‚±‚ê‚إˆہگS‚µ‚ؤ–»“r‚ة‚¢‚¯‚é‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚ـ‚·پv
پu‚¨•ê—l‚ج‚¨‰ءŒ¸‚حˆ«‚¢‚ج‚إ‚·‚©پv
پu‚¢‚¦پA‚»‚ê‚ھپcƒKƒ‰ƒNƒ^‚ًژج‚ؤ‚½‚猳‹C‚ة‚ب‚ء‚ؤپA‚ ‚ꂱ‚ꂤ‚邳‚Œ¾‚¤‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ
‚½پv
پu‚ب‚é‚ظ‚اپA‚»‚ê‚إپHپv
پu•ê‚ھگ´ژںکY‚ح•ذ•t‚¯‚ةŒü‚¢‚ؤ‚¢‚é‚©‚çپAƒTƒ|پ[ƒ^پ[‚جچuچہ‚ةچs‚ء‚ؤپA•×‹‚µ‚ؤ—ˆ‚¢‚ئ‚¢‚¤
‚à‚ج‚إپv
پ@گ\‚µچ‚ف‚جڈ‘—ق‚ة‚و‚é‚ئ”~گX‚ح62چخ‚إ‚ ‚éپB”~گX‚جŒ¾—t‚ھ‚ـ‚½“rگط‚ê’¾–ظ‚ھچL‚ھ‚ء‚½پB
پu”~گX‚³‚ٌپAˆê“xگ[Œؤ‹z‚ً‚µ‚ؤپAŒ¨‚ج—ح‚ً”²‚¢‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پv
‰ïڈê‚ح‚µ‚ٌ‚ئ‚µ‚ؤپA‚ھ‚ٌ‚خ‚ê‚ئ‚¢‚¤گ؛‚à‚ ‚è”~گX‚à‘ه‚«‚گ[Œؤ‹z‚ً‚µ‚½پB
‰½گl‚©‚ھپAژ©•ھ‚ج‚±‚ئ‚ج‚و‚¤‚ةگ[Œؤ‹z‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھŒ¨‚جڈم‰؛‚إ‚¤‚©‚ھ‚ي‚ꂽپB
پu‚µپAژdژ–‚حپc’·”Nˆَچü‰ïژذ‚إŒo—‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپAƒpƒ\ƒRƒ“‚إپc‘fگl‚إ‚à–¼ژh‚âˆَچü‚ھ
‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚èپA3”N‘O‚ة“|ژY‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚»‚êˆب—ˆ–³گE‚إ‚·پv
پu‚¨•ê—l‚ح‚ا‚¤‚µ‚ؤ•ذ•t‚¯‚ةŒü‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¨‚ء‚µ‚ل‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚©پv
‚‚çژq‚ج–â‚¢‚ةپA”~گX‚حڈ‚µڈئ‚ê‚ؤ“ڑ‚¦‚½پB
پu•ذ•t‚¯‚ج•û–@‚ھ‚ي‚©‚é‚ئپAٹy‚µ‚‚ب‚ء‚½‚©‚ç‚إ‚·پB‚ا‚±‚ة‰½‚ً‚ا‚¤‚¢‚¤•—‚ة’u‚‚ئژg‚¢‚â
‚·‚¢‚©پA•ذ•t‚¯‚â‚·‚¢‚©‚ًچl‚¦‚é‚ج‚ھ–ت”’‚‚ؤپA’I‚ً’ف‚ء‚½‚è‰ئ‹ï‚ج”z’u‚ً•د‚¦‚½‚è‚à‚µ‚ـ
‚µ‚½پB•ê‚ح‚»‚ê‚إٹى‚ر‚ـ‚µ‚½پv
پ@‚ـ‚ë‚ف‚ھƒ`ƒٹƒ“‚ئƒxƒ‹‚ً–آ‚炵‚½“r’[پAگب‚ة–ك‚낤‚ئ‚µ‚½”~گX‚ة”ڈژè‚ھ‹N‚±‚ء‚½پB
گM‚¶‚ç‚ê‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤ٹç‚إگ^‚ءگش‚ة‚ب‚ء‚½”~گX‚حگ[‚“ھ‚ً‰؛‚°‚½پB
پ@4”ش–ع‚ج—¤‰œŒcژq‚ح•¨‚¨‚¶‚µ‚ب‚¢گ«ٹi‚¾‚ء‚½پB
پu‚ي‚½‚µ‚ح’·”Nگê‹ئژه•w‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB•v‚ھ’è”N‚ة‚ب‚ء‚ؤپAچ،“x‚ح‚ي‚½‚µ‚ھ“‚”ش‚¾‚ئژv
‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚ئ‚ح‚¢‚¦ژè‚ةگE‚à‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚µپA‰½‚ً‚µ‚½‚ç‚و‚¢‚©‚ي‚©‚ç‚ب‚¢پB‚¾‚¯‚اڈ‚µ‚حگ¢
‚ج’†‚ج‚¨–ً‚ة—§‚آ‚±‚ئ‚ً‚µ‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚µ‚ؤپA‚ ‚éژdژ–‚ًچl‚¦‚½‚ج‚إ‚·پB‚ب‚ٌ‚¾‚ئژv‚ي‚ê‚ـ
‚·‚©پv
پ@Œcژq‚ھژَچuژز‚ً‚ن‚ء‚‚茩‚ـ‚ي‚µ‚½پBژ©•ھ‚ج”ش‚ھڈI‚ي‚ء‚½‘هژR‚حژ©گM–پX‚إ“ڑ‚¦‚½پB
پu•ذ•t‚¯ƒTƒ|پ[ƒ^پ[‚جژdژ–‚إ‚µ‚ه‚¤پv
پuˆل‚¤‚ٌ‚إ‚·پv
Œcژq‚حˆêŒؤ‹z’u‚¢‚ؤپAٹF‚ج”½‰‚ًٹy‚µ‚ٌ‚إ‚¢‚½پB
پuژہ‚ح“®•¨’T’م‚ً‚µ‚و‚¤‚ئژv‚ء‚½‚ج‚إ‚·پv
‰½‚¾پA‚»‚è‚ل‚ئ‚¢‚¤گ؛‚ھ‚ ‚ھ‚ء‚½پB
پu‚¢‚ب‚‚ب‚ء‚½ƒyƒbƒg‚ً’T‚·’T’م‚إ‚·‚وپBƒVƒƒپ[ƒچƒbƒNپEƒzپ[ƒ€ƒY‚ف‚½‚¢‚بپv
‚ ‚ح‚ح‚ح‚âپA‚¨‚ظ‚ظ‚ئ‚¢‚¤ڈخ‚¢گ؛‚ھ‹N‚±‚ء‚½پB
ƒzپ[ƒ€ƒY‚ھƒyƒbƒg’T‚µ‚ً‚·‚é‚©‚ث‚¦‚ئ‚¢‚¤‚آ‚ش‚â‚«‚à‚ ‚ء‚½پB
پuٹF‚³‚ٌڈخ‚¢‚ـ‚·‚¯‚اپA‚ي‚½‚µ‚حگ^Œ•‚¾‚ء‚½‚ٌ‚إ‚·پB‚»‚ê‚إچs•û•s–¾‚جƒyƒbƒg‚ً’T‚µ‚ـ‚·‚ئ
‚¢‚¤ƒ`ƒ‰ƒV‚ًچى‚ء‚ؤƒXپ[ƒpپ[‚ج“`Œ¾”آ‚ة’£‚ء‚ؤ‚à‚ç‚¢‚ـ‚µ‚½پv
پuˆث—ٹ‚ح‚ ‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚©پv‚ئˆê”ش‘O‚ةچہ‚ء‚ؤ‚¢‚éŒK–ىŒُ‘م‚ھژv‚ي‚¸گq‚ث‚½پB
پu‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ê‚àژںپX‚ئپv
پ@‚»‚ê‚ب‚ç‚ب‚؛‚±‚±‚ة‚¢‚é‚ج‚©پA‚ئ‚¢‚¤‹^–â‚ة“ڑ‚¦‚é‚و‚¤‚ةŒcژq‚ح‘±‚¯‚½پB
پuˆث—ٹ‚ح‚½‚‚³‚ٌ‚ ‚邯‚ê‚اپAچs•û•s–¾‚جƒyƒbƒg‚ً1•C‚àŒ©‚آ‚¯‚ç‚ê‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إ‚·پB‚¾‚©‚ç
‚¨‹à‚à‚à‚炦‚ب‚©‚ء‚½پv
پ@کb‚µ‚ب‚ھ‚çŒcژq‚ح‚¤‚ب‚¾‚ꂽپB‚±‚ê‚ة‚حٹFگپ‚«ڈo‚µ‚½پB”~گX‚àŒû‚ًٹJ‚¯‚ؤڈخ‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
پu‚»‚¤‚ب‚ٌ‚إ‚·پBگlٹش‚ب‚çچs•û•s–¾‚إ‚àپA’m‚èچ‡‚¢‚ئ‚©‚¢‚ë‚¢‚ë’T‚·ژè—§‚ؤ‚ھ‚ ‚é‚و‚¤‚إ‚·
‚ھپA“®•¨‚ح‚µ‚ل‚ׂء‚ؤ‚‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚©‚ç‚ثپB‚ي‚½‚µ‚ھŒxژ@Œ¢‚ف‚½‚¢‚ة•@‚ھ‚«‚¢‚½‚çڈ‚µ‚حˆل‚ء
‚½‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAŒ¢‚â”L‚جژتگ^‚ًژ‚ء‚ؤ‚¤‚낤‚낵‚ؤ‚à–¼ڈو‚èڈo‚ؤ‚‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ
‚½پv
‰ïڈê‚ح‘ه”ڑڈخ‚إپA—ـ‚ً—¬‚µ‚ؤ‚¢‚éژز‚à‚¢‚½پB
پu‚»‚ê‚إ•v‚ھپAŒ¢”L‚ً’T‚µ‚ـ‚ي‚é‚و‚è‰ئ‚ج’†‚ً•ذ•t‚¯‚ë‚ئ“{‚è‚ـ‚µ‚½پB‚ي‚½‚µ‚حƒJƒb‚ئ‚ب‚ء
‚ؤپAژ©•ھ‚à‰ئ‚ة‚¢‚é‚ٌ‚¾‚©‚çژ©•ھ‚إ•ذ•t‚¯‚ب‚³‚¢‚و‚ئŒ¾‚¤‚ئپA‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚إ‚«‚é‚©‚ئŒ¾‚¤‚ٌ
‚إ‚·پB‚ا‚¤ژv‚¢‚ـ‚·پHپ@‘هژR‚³‚ٌ‚â”~گX‚³‚ٌ‚ج’ـ‚جچC‚إ‚àگ÷‚¶‚ؤˆù‚ـ‚¹‚ؤ‚â‚肽‚¢‚إ‚·‚وپv
‘هژR‚حپA‚¨‚ظ‚ٌ‚ئ‚¤‚ꂵ‚»‚¤‚ةٹP•¥‚¢‚ً‚µ‚½پB
پu‚ي‚½‚µ‚ح‚à‚ئ‚à‚ئ•ذ•t‚¯‚ھ‹êژè‚ب‚ج‚إپA‚»‚ê‚ب‚ç•ذ•t‚¯چuچہ‚ًژَ‚¯‚é‚©‚çپAژَچu—؟‚ًڈo‚µ
‚ؤ‚ئ‚¢‚¤‚ئپA‚ا‚¤‚µ‚ؤ•ذ•t‚¯‚ًڈK‚¢‚ةچs‚©‚ب‚«‚ل‚ب‚ç‚ب‚¢‚ٌ‚¾‚ئگ\‚µ‚ـ‚·پB‚±‚ꂾ‚©‚çڈ—‚ح
چ¢‚é‚ئ‚©پAگ¢‚ج’†‚ج‚±‚ئ‚ً‚ي‚©‚ء‚ؤ‚ب‚¢‚ئ‚©پA‚ظ‚ٌ‚ئگخ“ھ‚ب‚ٌ‚¾‚©‚çپv
پ@‚±‚±‚إپA‚ح‚¢ژٹش‚إ‚·‚ئƒ`ƒٹƒ“‚ھ–آ‚ء‚½پB
ƒTƒ|پ[ƒ^پ[ژEگlژ–Œڈ(2)‚ة‘±‚
 پ@
پ@

‚±‚جکb‚جƒ^ƒCƒgƒ‹‚حپAŒ³‚حپuƒAƒhƒoƒCƒUپ[چuچہپv‚إ‚µ‚½‚ھƒ~ƒXƒeƒٹپ[چD‚«‚ھچ‚‚¶‚ؤپuƒTƒ|پ[
ƒ^پ[ژEگlژ–Œڈپv‚ة‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پB(‹êڈخپj
‚»‚ê‚ة‚±‚جکb‚ح‚à‚ج‚·‚²‚’·‚¢‚إ‚·پB‘¼‚جکb‚جگ””{پB
ƒuƒچƒOڈ¬گà‚إڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚½ژ‚حپA–ˆ“ْڈ‚µ‚¸‚آڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپA’·‚‚ب‚é‚ئ‘O‚جکb‚ھ‚ا‚¤‚¾‚ء
‚½‚©‚ي‚©‚ç‚ب‚‚ب‚邵پA‘k‚é‚ج‚à‘ه•د‚ب‚ج‚إ”نٹr“I’Z‚‚ـ‚ئ‚ك‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚·‚ھپA‚±‚جکb‚حڈ‘
‚«ڈo‚·‚ئژ~‚ـ‚ç‚ب‚‚ب‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‚©پA–ت”’‚‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB
‚»‚ê‚ةگl‚ً1گlژE‚·‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA‚¨کb‚ة‚µ‚ؤ‚à‘ه•د‚إپA‚±‚¤‚µ‚ؤ’·‚‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB
‚µ‚©‚µ‚±‚ج‚و‚¤‚ةژ©ژذ‚جHP‚¾‚ئ‚ ‚é’ِ“x‚ج—ت‚ھڈ‘‚¯‚ـ‚·‚µپAڈ‘‚¢‚ؤ‚à’N‚ة‚à–ہکf‚ً‚©‚¯‚ب‚¢
‚ئ‚¢‚¤‚©پA‚¢‚آ‚إ‚à“ا‚ك‚邵پA“ا‚ف‚½‚¢گl‚¾‚¯“ا‚ٌ‚إ‚¢‚½‚¾‚¯‚ê‚خ‚و‚¢‚©‚çپA‚±‚ê‚حژ©•ھ‚إ
HP‚ً‚آ‚‚é—ک“_‚¾‚ب‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
 پ@
پ@
پ@پu‚‚炵‚©‚éپvپi‚g‚o‚Qپjپ@‚²ˆؤ“àپ@
پ@

 |
 |
||||
 |
 |
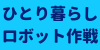 |
پ@پu‚‚炵‚©‚éپvپi‚g‚o‚Pپjپ@‚²ˆؤ“àپ@
پ@
 ‚g‚o‚Pƒwپ@پ@پ@ پ@پ@
‚g‚o‚Pƒwپ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
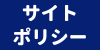 |
 |
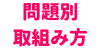 |
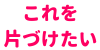 |
پ@
پںپuکV‘Oگ®—پv‚ح(ٹ”پj‚‚炵‚©‚é‚ج“oک^ڈ¤•W‚إ‚·پB–³’f‚إ‚جڈ¤—p—ک—p‚ح‚¨’f‚肵‚ـ‚·پB